2021/07/14 (WED)
アメリカ~フランス~ロシア・中国・イギリス 「異文化体験を語る」連続講演会5月編開催
OBJECTIVE.
コロナウイルス禍で海外への渡航もままならぬ中、学生のみなさんに遠く広い世界への夢と意思を持ち続けてもらうべく、社会学部専任教員がオムニバス形式でそれぞれの<世界体験>を披瀝する「異文化体験を語る」連続講演会(社会学部国際化推進委員会主催)は、5月、3度(第1~3回)にわたって昼休みにオンラインで行われた。
アメリカNY州 日本にいない専門研究者探し求めて 第1回 木村忠正教授
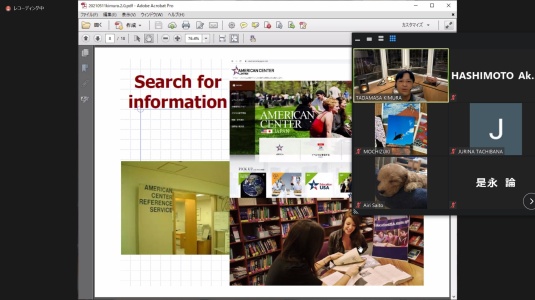
当日配信画像より
5月11日(火)第1回講演会は、メディア社会学科の木村忠正教授が、「Time trip to 30 years ago(30年前へのタイムトリップ)」と題し、1990年代前半にアメリカ大学院留学した経験を起点として、ここ30年間の日本人の米高等教育機関留学と取り巻く社会環境の変化について話をしてくれた。
大学院生時代、専門特殊性が高い「認知人類学」に強い関心を持っていたが、日本ではほとんど専門とする研究者がいなかった。そこで、当該分野の中心的研究者の一人(Dr. Charles Frake)が、ちょうどスタンフォード大からニューヨーク州立大バッファロー校(SUNY at Buffalo, UB)に移動したことを知り、UBに1990年留学した。当時は、米大学でもインターネット以前であり(ホワイトハウスホームページが開設されたのが1994年10月)、日本で情報収集するときは、アメリカ大使館のアメリカンセンターに足繁く通い、紙資料と郵便ですべてやりとりしなければならなかった。
時代背景を振り返ると、1985年プラザ合意によって、円高が急激に進み(合意前1ドル260円程度から88年には120円台まで、円の価値は3年で倍以上に)、80年代後半のバブル経済を生み出すとともに、海外旅行、留学が拡がり始める時期にあたっていた。日本人留学生数は89年に2万人を初めて越え、90年代を通して増加して、2003年には8万人に達する。米高等教育機関への留学生(短期ではなく正規課程修学者)に占める日本人の割合も4%程度からピーク時には10%(94年度)を超えて、世界で最多地域であった(45万人中の4.5万人強)。冷戦終結時、自由主義世界は、アメリカ(2.5億人)、欧州(英独仏で2億人)、日本(1.2億人)が三極を形成し、科学技術研究においても、日本はグローバル社会で主要な地位を占めていたのである。
その後、21世紀、グローバル化が進展する中で、日本社会は相対的に縮小しつつある。2020年の米高等教育機関留学生(正規課程修学)は100万人強だが、中国が35%、インドが18%と2地域で過半を占め、日本からは1.7万人と2%に満たない(短期交換留学生は日本全体で10万人と増加しているが)。日本社会がこれからも縮小均衡を続けることを念頭に置くと、いまの大学生には、日本という枠に囚われず、グローバル社会で活動できる力を身につけて欲しいと、参加者たちに強く伝えた。
質疑応答の中で、米大学院時代が、寮生活をはじめ、大学以降の学生生活では、最も楽しく、充実していたこと、米大学院教育は、学期中は「生き残り(survival)」という表現が本当にピッタリするほど過酷だが、学期毎に知的成長を実感できる環境だったことなど、厳しさと楽しさが語られた。もっとも、米高等教育は、費用が2000年代高騰しており、州立でも、現在は年300万円~500万円にも達しているデータも示された。また、文化人類学は、異文化社会に研究者が赴き、現地の人と交流する学問なので、文化人類学部の教員、院生たちは、留学生に対してとても親しく接してくれたが、同年代で経済学で留学した人には、競争意識が激しく、嫌な思いを経験する研究者も少なくなかったといった学術領域毎の違いも語られた。
大学院生時代、専門特殊性が高い「認知人類学」に強い関心を持っていたが、日本ではほとんど専門とする研究者がいなかった。そこで、当該分野の中心的研究者の一人(Dr. Charles Frake)が、ちょうどスタンフォード大からニューヨーク州立大バッファロー校(SUNY at Buffalo, UB)に移動したことを知り、UBに1990年留学した。当時は、米大学でもインターネット以前であり(ホワイトハウスホームページが開設されたのが1994年10月)、日本で情報収集するときは、アメリカ大使館のアメリカンセンターに足繁く通い、紙資料と郵便ですべてやりとりしなければならなかった。
時代背景を振り返ると、1985年プラザ合意によって、円高が急激に進み(合意前1ドル260円程度から88年には120円台まで、円の価値は3年で倍以上に)、80年代後半のバブル経済を生み出すとともに、海外旅行、留学が拡がり始める時期にあたっていた。日本人留学生数は89年に2万人を初めて越え、90年代を通して増加して、2003年には8万人に達する。米高等教育機関への留学生(短期ではなく正規課程修学者)に占める日本人の割合も4%程度からピーク時には10%(94年度)を超えて、世界で最多地域であった(45万人中の4.5万人強)。冷戦終結時、自由主義世界は、アメリカ(2.5億人)、欧州(英独仏で2億人)、日本(1.2億人)が三極を形成し、科学技術研究においても、日本はグローバル社会で主要な地位を占めていたのである。
その後、21世紀、グローバル化が進展する中で、日本社会は相対的に縮小しつつある。2020年の米高等教育機関留学生(正規課程修学)は100万人強だが、中国が35%、インドが18%と2地域で過半を占め、日本からは1.7万人と2%に満たない(短期交換留学生は日本全体で10万人と増加しているが)。日本社会がこれからも縮小均衡を続けることを念頭に置くと、いまの大学生には、日本という枠に囚われず、グローバル社会で活動できる力を身につけて欲しいと、参加者たちに強く伝えた。
質疑応答の中で、米大学院時代が、寮生活をはじめ、大学以降の学生生活では、最も楽しく、充実していたこと、米大学院教育は、学期中は「生き残り(survival)」という表現が本当にピッタリするほど過酷だが、学期毎に知的成長を実感できる環境だったことなど、厳しさと楽しさが語られた。もっとも、米高等教育は、費用が2000年代高騰しており、州立でも、現在は年300万円~500万円にも達しているデータも示された。また、文化人類学は、異文化社会に研究者が赴き、現地の人と交流する学問なので、文化人類学部の教員、院生たちは、留学生に対してとても親しく接してくれたが、同年代で経済学で留学した人には、競争意識が激しく、嫌な思いを経験する研究者も少なくなかったといった学術領域毎の違いも語られた。
アメリカ~フランス Les faux amis 偽りの友人たち 第2回 橋本晃教授

当日配信画像より
5月18日、第2回講演会では、メディア社会学科の橋本晃教授が「Les faux amis 偽りの友人たち——米仏2つの文明の狭間で」と題して、大学院留学したアメリカ中西部と特派員として駐在したフランス・パリでの経験を踏まえて、欧米とひと口に言ってしまいがちだが相当に原理の異なる2文明のさまざまな貌を紹介し、「複眼的な視点、歩行の一歩一歩が<世界認識>の深化・拡大につながるような日々を」と訴えた。
講演ではまず、冷戦終結後、力の均衡が崩れた世界のあちこちで地域紛争、民族紛争が噴出していた1990年代、国際報道に従事し、イスラエル・パレスチナ、カンボジア、南アフリカでの長期取材を経て、アメリカのジャーナリズム大学院に留学した経緯が語られた。「選んだのは中西部アイオワ、周囲を玉蜀黍畑に囲まれた小さな大学町です」
アイオワシティを選んだ理由について、橋本教授はジャーナリズム・マスコミュニケーション研究の中心は中西部の州立大学であること、ハートランド・中西部には印刷機を馬車に積んで開拓の町にやってきた印刷職人=新聞発行者と草の根のジャーナリズムの神話が生きていることなどを挙げたうえで、「現存するアメリカの作家の3分の1が学生、フェロー、教員として籍を置いたといわれる全米最古の創作科・アイオワライターズワークショップも覗いてみたかった」橋本教授がかつて訳書を上梓した女性作家ジェーン・アン・フィリップスや敬愛してやまない中上健次もアイオワにいた。「アイオワシティは自分にとって約束の地だったのです」
アメリカ留学のあと、勤務していた新聞社からパリに特派員として派遣された。内示を受けたときは少しとまどったという。「ジャーナリズムのプラクティスよりもジャーナリズム自体をその根源まで遡って考える作業に気持ちがシフトしつつあった」しかし、一方で「アメリカだけでなくヨーロッパ、特に非英語圏のフランスを見たかった。「学部は仏文科でしたし」
二度目の外国生活だったが、パリ暮らしは「迷宮の中を彷徨っているようだった」アパルトマンを見つけて入居するまで2か月半かかった。入国から3か月以内に査証を滞在許可証に切り替えねばならないが、窓口の職員は週の初めや終わり、1日の初めと終わり、さらにはお昼休みの前後もやる気がなく機嫌も悪く、なかなか手続きが進まない。日常的なクレジットカードの二重引き落としや新聞の欠配。オフィスの入るビルの屋上にパラボラアンテナを設置するのに半年かかり、最初に住んだアパルトマンを退去するのに生まれて初めて弁護士を立てた。そんなときでも、フランス人はいかにも他人事のように「C’est pas grave (たいしたことない)」という。
しかし、パリ郊外にある20世紀前半の銀行家、アルベール・カーンの資料館で、第一次世界大戦の西部戦線で徴兵された農民の兵士たちが「もっとまともなパンを、もっとまともなワインをよこせ」とストを起こしたとき、パリの軍トップは「わかった」と前線の兵士たちにパンとワインを送ったエピソードを知った。「戦場でのストも、それに応じる軍司令部も、ほかの国ではついぞ見られない。戦争には負けるけれど、いい国だなと思いました」
フランスもアメリカも「欧米」とひとくくりにしがちだが、あまりにも異なった2つの文明。それは仏語と英語で綴りが同じかほぼ同じだが意味はすれ違う語彙の総称「les faux amis (偽りの友人たち)」に表れている。この洒落た、アイロニカルな表現自体もフランス文明の真骨頂だ。
いまも、アメリカとフランスの2国を行き来するという橋本教授は、「複眼的な視点を大切に。そして、歩行の一歩一歩が<世界>認識の深化・拡大につながるような日々を」との言葉で講演を締めくくった。
講演ではまず、冷戦終結後、力の均衡が崩れた世界のあちこちで地域紛争、民族紛争が噴出していた1990年代、国際報道に従事し、イスラエル・パレスチナ、カンボジア、南アフリカでの長期取材を経て、アメリカのジャーナリズム大学院に留学した経緯が語られた。「選んだのは中西部アイオワ、周囲を玉蜀黍畑に囲まれた小さな大学町です」
アイオワシティを選んだ理由について、橋本教授はジャーナリズム・マスコミュニケーション研究の中心は中西部の州立大学であること、ハートランド・中西部には印刷機を馬車に積んで開拓の町にやってきた印刷職人=新聞発行者と草の根のジャーナリズムの神話が生きていることなどを挙げたうえで、「現存するアメリカの作家の3分の1が学生、フェロー、教員として籍を置いたといわれる全米最古の創作科・アイオワライターズワークショップも覗いてみたかった」橋本教授がかつて訳書を上梓した女性作家ジェーン・アン・フィリップスや敬愛してやまない中上健次もアイオワにいた。「アイオワシティは自分にとって約束の地だったのです」
アメリカ留学のあと、勤務していた新聞社からパリに特派員として派遣された。内示を受けたときは少しとまどったという。「ジャーナリズムのプラクティスよりもジャーナリズム自体をその根源まで遡って考える作業に気持ちがシフトしつつあった」しかし、一方で「アメリカだけでなくヨーロッパ、特に非英語圏のフランスを見たかった。「学部は仏文科でしたし」
二度目の外国生活だったが、パリ暮らしは「迷宮の中を彷徨っているようだった」アパルトマンを見つけて入居するまで2か月半かかった。入国から3か月以内に査証を滞在許可証に切り替えねばならないが、窓口の職員は週の初めや終わり、1日の初めと終わり、さらにはお昼休みの前後もやる気がなく機嫌も悪く、なかなか手続きが進まない。日常的なクレジットカードの二重引き落としや新聞の欠配。オフィスの入るビルの屋上にパラボラアンテナを設置するのに半年かかり、最初に住んだアパルトマンを退去するのに生まれて初めて弁護士を立てた。そんなときでも、フランス人はいかにも他人事のように「C’est pas grave (たいしたことない)」という。
しかし、パリ郊外にある20世紀前半の銀行家、アルベール・カーンの資料館で、第一次世界大戦の西部戦線で徴兵された農民の兵士たちが「もっとまともなパンを、もっとまともなワインをよこせ」とストを起こしたとき、パリの軍トップは「わかった」と前線の兵士たちにパンとワインを送ったエピソードを知った。「戦場でのストも、それに応じる軍司令部も、ほかの国ではついぞ見られない。戦争には負けるけれど、いい国だなと思いました」
フランスもアメリカも「欧米」とひとくくりにしがちだが、あまりにも異なった2つの文明。それは仏語と英語で綴りが同じかほぼ同じだが意味はすれ違う語彙の総称「les faux amis (偽りの友人たち)」に表れている。この洒落た、アイロニカルな表現自体もフランス文明の真骨頂だ。
いまも、アメリカとフランスの2国を行き来するという橋本教授は、「複眼的な視点を大切に。そして、歩行の一歩一歩が<世界>認識の深化・拡大につながるような日々を」との言葉で講演を締めくくった。
「めぐり合わせ」から考えた異文化体験 第3回 是永論教授

アイスホッケーチームのメンバーと(前列一番左が是永教授)
5月26日第3回講演会は、メディア社会学科の是永論教授が「私流「受け身技」の異文化体験」というタイトルで、海外留学経験のない立場から、自身の海外体験を「受け身技」として独自に特徴づけながら語るものであった。
まず、柔道での受け身技の動画を示しながら、「受け身」について、キャリアの自主的な追求や積極的な勉強といった経験ではなく、「なりゆき」から身についた経験を意味すると同時に、自身が実際に自転車で転倒した時に受け身技で怪我を免れた話から、何かの失敗に対して「転んだ時の備えfail safe」を示すという意味が説明された。
そこから大学時代の最初の異文化経験として、4カ国語(英語、ロシア語、フランス語、中国語)を同時履修したためにどれも身につかず、1年後中国とロシア(当時ソ連)を40日かけて旅行した際にも全く通用しなかったという「失敗」が、15歳にして英語だけを駆使して東欧諸国を単独で歴訪した佐藤優さんの『15の夏』(幻冬舎)での成功例を引き合いに語られた。その後は30代から映画や音楽などによりアジア文化との関わりを深める一方で、韓国語の現地での集中学習や、韓国の方との交流の中で異文化経験に恵まれたという。
40代からのイギリスでの長期滞在については、スポーツでの経験を中心に、サッカー観戦に行って、選手に対する人種差別発言を目にしただけでなく、自身にもその発言が向けられたことや、20代の大学生に混じってアイスホッケーの試合に出て激しい体当たりをくらうなどの、特殊な体験が披露された。
まとめのことばとして、語学に覚えがなくても、その場にいることが何かの役に立つこともあるのだから自信をもっていいし、逆に「異邦人 étranger」という立場から、めぐり合わせで得られることもある、というメッセージが、イギリス滞在中に現地ネイティブの人から打ち明け話を聞いた経験とともに示された。
聴衆の方からは、セカンドステージ大学の方の「昔のカンボジアでの駐在体験と重なるところがあった」という声や、アンケートでは「就活などで前のめりになるばかりで自分に余裕が持てない中、めぐり合わせもあるのだから、思いつめずに過ごしたいと思えました」という感想が寄せられ、さまざまな世代に対してそれぞれの立場に合った印象を残したようだった。
まず、柔道での受け身技の動画を示しながら、「受け身」について、キャリアの自主的な追求や積極的な勉強といった経験ではなく、「なりゆき」から身についた経験を意味すると同時に、自身が実際に自転車で転倒した時に受け身技で怪我を免れた話から、何かの失敗に対して「転んだ時の備えfail safe」を示すという意味が説明された。
そこから大学時代の最初の異文化経験として、4カ国語(英語、ロシア語、フランス語、中国語)を同時履修したためにどれも身につかず、1年後中国とロシア(当時ソ連)を40日かけて旅行した際にも全く通用しなかったという「失敗」が、15歳にして英語だけを駆使して東欧諸国を単独で歴訪した佐藤優さんの『15の夏』(幻冬舎)での成功例を引き合いに語られた。その後は30代から映画や音楽などによりアジア文化との関わりを深める一方で、韓国語の現地での集中学習や、韓国の方との交流の中で異文化経験に恵まれたという。
40代からのイギリスでの長期滞在については、スポーツでの経験を中心に、サッカー観戦に行って、選手に対する人種差別発言を目にしただけでなく、自身にもその発言が向けられたことや、20代の大学生に混じってアイスホッケーの試合に出て激しい体当たりをくらうなどの、特殊な体験が披露された。
まとめのことばとして、語学に覚えがなくても、その場にいることが何かの役に立つこともあるのだから自信をもっていいし、逆に「異邦人 étranger」という立場から、めぐり合わせで得られることもある、というメッセージが、イギリス滞在中に現地ネイティブの人から打ち明け話を聞いた経験とともに示された。
聴衆の方からは、セカンドステージ大学の方の「昔のカンボジアでの駐在体験と重なるところがあった」という声や、アンケートでは「就活などで前のめりになるばかりで自分に余裕が持てない中、めぐり合わせもあるのだから、思いつめずに過ごしたいと思えました」という感想が寄せられ、さまざまな世代に対してそれぞれの立場に合った印象を残したようだった。
