教員研究・教員
社会学科
イシカワ リョウコ
石川 良子
教授
社会学科

主な担当科目 コミュニケーション論
研究テーマ ライフストーリー研究
主な業績
『「ひきこもり」から考える』(ちくま新書、2021年)
『ひきこもりの〈ゴール〉』(青弓社、2007年)
『「ひきこもり」の30年を振り返る』(岩波ブックレット、2023年。林恭子・斎藤環との共著)
『ライフストーリー研究に何ができるか』(新曜社、2015年。桜井厚との共編著)
連絡先 iskwryk@rikkyo.ac.jp
社会学は「“あたりまえ”にツッコミを入れる学問」だと考えています。冴えたツッコミはボケを輝かせます。“あたりまえ”にうまくツッコミを入れられるようになれば、社会はとても面白く魅力的なものに見えてくるはずです。また、しんどい状況に巻き込まれてしまったときも、そんな状況にツッコミを入れてみると、このしんどさは自分自身のせいではないと少し気持ちが軽くなったり、折り合いをつけていく道筋がほんのり見えてきたりします。よりよく生きていくためのツールとして一緒に社会学を学んでいきましょう。
イ ミンジン
李 旼珍
教授
社会学科

主な担当科目 労働社会学、比較社会論
研究テーマ フレキシブルな資本主義における新しい雇用形態やワークシステムのもとで、労働者は主体的に、自律的に働けるか、また働きすぎるのはなぜなのか、などについてアメリカ、日本、韓国を研究フィールドとし、研究している
主な業績
『賃金決定制度の韓日比較』(単著)梓出版社、2000年
『現代社会学における歴史と批判—グローバル化の社会学』(共著)東信堂、2003年
「職場における新しい労働統制——電子監視とパノプティコン・メタファー」(単著)、『応用社会学研究』48号、2006年
連絡先 leemj@rikkyo.ac.jp
「世界に一つの存在になりなさい」だけではなく、「世界や社会の中の一員として成長・発展することが重要である」ことを気づかせる学問が社会学です。社会学とともに、社会の中で大きく成長してください。
オサ ユキエ
長 有紀枝
教授
社会学科

主な担当科目 人間の安全保障とNGO、紛争と和解・共生
研究テーマ 人間の安全保障、平和構築、国際人道法、ジェノサイド研究など。
主な業績
『スレブレニツァーあるジェノサイドをめぐる考察』(単著)東信堂、2009年
『地雷問題ハンドブック』(単著)自由国民社、1997年
『国際緊急人道支援』(共著)ナカニシヤ出版、2008年
『国家建設における民軍関係破綻国家再建の理論と実践をつなぐ』(共著)国際書院、2008年
連絡先 yukieosa@rikkyo.ac.jp
かけがえのない4年間、自分と関係のない世界の、関係のない人々の暮らしに対しても、わがことのように思いをはせる「想像力」と、「なぜ?どうして?」という「知的好奇心」を一緒に高めていきましょう。
カタカミ ヘイジロウ
片上 平二郎
教授
社会学科

主な担当科目 社会学原論1 社会学理論
研究テーマ 理論という抽象的な道具を用いたからこそ見えてくる社会の姿について考えたいと思い、テオドール.W.アドルノの思想を主に理論社会学的な研究を行っています。その際に、アイデンティティとコミュニケーション、文化といった観点を大事にしたいと思っています。近年は、日本における社会学の歴史についても興味を持ち、研究をはじめています。
主な業績
『アドルノという「社会学者」』(単著)晃洋書房、2018年
『ポピュラーカルチャー論「講義」』(単著)晃洋書房、2017年
連絡先 katakami@rikkyo.ac.jp
人間は誰しもが社会の中を生きており、だからこそ、時に社会と衝突をして、社会について考えざるを得ない局面を迎えることになるはずです。社会学は、そんなときに単なる知識であることを越えて、もっと生々しいかたちでみなさんの人生に関わってくるものとなるはずです。真面目に、でも、楽しく、社会学という独特の魅力をもった学問についてみなさんと考えていきたいと思っています。
クラモト ユキコ
倉本 由紀子
教授
社会学科

主な担当科目 国際関係論 開発・発展の社会学
研究テーマ 国際社会学、社会開発とジェンダー、グローバル・ガバナンス
主な業績
『現代社会の信頼感 : 国際比較研究(II)』第2章「グローバル・ガバナンスと『信頼感』」中央大学出版 2018
『開発リスクの政治経済的研究』第6章「開発リスクとジェンダー」文眞堂 2013
「ジェンダー不平等指数(GII)分析とジェンダー・エンパワーメント尺度(GEM)修正版作成の試み」『国際ジェンダー学会誌』(10)53–73
連絡先 y.kuramoto@rikkyo.ac.jp
「世界は狭い!」と感じたことはありますか?21年間の在米生活中も、まさかのタイミングと場所で、人と再会し「人と人のつながり」に驚嘆したことが何度もあります。今後の地球社会において、ビジネス活動や国際協働に必要な「信用」や「信頼」を醸成し、グローバル・ネットワークを広げる努力をすることは、学生さんたちにとって、将来かけがいない財産になると思います。多様なバックグラウンドをもつ人々との「縁」を大切にし、「グローバル市民」としての役割を自覚して、山積する地球規模の諸問題について一緒に考えることができたら嬉しいです。
スギウラ イクコ
杉浦 郁子
教授 / 学科長
社会学科

主な担当科目 ジェンダーの社会学
研究テーマ 日本における性的マイノリティの社会運動
主な業績 『「地方」と性的マイノリティ:東北6県のインタビューから』(青弓社、2022年、前川直哉氏との共著) 『レズビアン雑誌資料集成』(不二出版、2024年、編集・解説を担当)
連絡先 uraiku@rikkyo.ac.jp
ジェンダーやセクシュアリティについて社会学的に学ぶという営みは、格差や差別について思考を深めることと不可分です。性に関する固定観念やそれにもとづく諸制度がどのように格差や差別を生み出しているのか。不正義のある現状を変えていくために社会の一員として何ができるのか。共に考えていきましょう。
タカヤマ マコト
高山 真
助教
社会学科

主な担当科目 質的調査法、社会問題の社会学、専門演習1、社会調査法2
研究テーマ 物語と〈語りえないもの〉の関係に着目し、ライフストーリーを聞くという質的調査の方法から自己について考えています。これまでの研究では、長崎における被爆者とのライフストーリー・インタビューに携わってきました。これからは、他者との出会いにともない対話的に構成される〈わたし〉という現象について新たなフィールドワークを視野にいれて考えていきたいと思います。
主な業績
『アート・ライフ・社会学 エンパワーするアートベース・リサーチ』(共著)晃洋書房、2020年
『〈被爆者〉になる 変容する〈わたし〉のライフストーリー・インタビュー』(単著)せりか書房、2016年
『過去を忘れない 語り継ぐ経験の社会学』(共著)せりか書房、2008年
連絡先 makoto.takayama@rikkyo.ac.jp
わたくしといふ現象は仮定された有機交流電燈のひとつの青い照明です。宮沢賢治の詩を読むことも社会学につながります。楽しく学びましょう。
ナカザワ ワタル
中澤 渉
教授
社会学科

主な担当科目 現代社会変動論、専門演習、教育社会学演習
研究テーマ 教育社会学、社会階層論、計量社会学
主な業績
中澤渉・野村晴夫編『学ぶ・教える(シリーズ人間科学4)』大阪大学出版会、2020年
中澤渉『日本の公教育-学力・コスト・民主主義』中央公論新社、2018年
中澤渉『なぜ日本の公教育費は少ないのか-教育の公的役割を問いなおす』勁草書房、2014年
連絡先 wnakazawa@rikkyo.ac.jp
大学4年間は、長いようであっという間です。いろいろな人と出会い、たくさんの本を読み、様々な経験を積んでください。社会学を学ぶ上で、それらはすべて役に立つはずです。大学生活は自由ですが、自由であるということは、大学生活が有意義なものになるか否かも、かなりの程度学生本人の姿勢に依存するということを意味します。若い時に、失敗を恐れず、多くの挑戦をしてもらいたいと思います。
ニシヤマ シホ
西山 志保
教授
社会学科

主な担当科目 公共性の社会学、地域社会学
研究テーマ 専門は、都市社会学、まちづくり論、NPO/NGO/社会的企業研究。地域住民が主体となって行政や企業と協働しながら行う、まちづくりやコミュニティ再生の実態調査やコミュニティ・ガバナンスの国際比較研究を行っています。日本を初め、欧米の様々なコミュニティを訪れ、独自の社会制度、文化的背景の中で、人々がどのように‘まちづくり’を展開させているのかを研究しています。
主な業績
『改訂版ボランティア活動の論理』(単著)東信堂、2007年
「ガバナンスを導く協働(パートナーシップ)の可能性」(単著)『社会政策研究7』、2007年
『イギリスのガバナンス型まちづくり』(共著)学芸出版、2008年
『分断社会と都市ガバナンス』(共著)、日本経済評論社、2011年
連絡先 snishiyama@rikkyo.ac.jp
コミュニティで発生している複雑な社会問題に目を向け、その背景にある「社会的真実」を見抜く目を養ってください。コミュニティとは、人と人がつながる「場」であり、新たな発見がたくさんある「可能性の場」です。
ノロ ヨシアキ
野呂 芳明
教授
社会学科
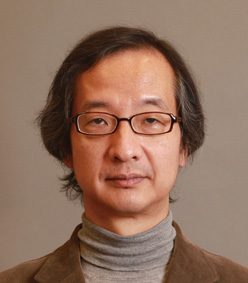
主な担当科目 現代社会と政策、社会学データ実習
研究テーマ 現代都市社会論、高齢者福祉研究、まちづくり研究
主な業績
『生きがいの社会学—高齢社会における幸福とは何か』(共著)弘文堂、2001年
『高齢期と社会的不平等』(共著)東京大学出版会、2001年
連絡先 edwin@rikkyo.ac.jp
社会を学ぶためには、積極的に外に出て見聞を広めること、自分とはちがう他者と交流する経験が不可欠です。そのためにゼミだからこそ可能な機会をつくっていきますので、いい意味でそれを利用し、文献研究と合わせて自分の問題意識を深めてください。
ホンダ マサタカ
本多 真隆
准教授
社会学科

主な担当科目 家族社会学、専門演習、家族社会学演習
研究テーマ 家族社会学、歴史社会学、家族研究学説史
主な業績
本多真隆『家族情緒の歴史社会学:「家」と「近代家族」のはざまを読む』晃洋書房、2018年。
『基礎からわかる社会学研究法:具体例で学ぶ研究の進め方』ミネルヴァ書房、2023年(松木洋人、中西泰子との共編著)。
連絡用メールアドレス masataka-honda@rikkyo.ac.jp
大学という場でこそ体験できることはたくさんあります。落ち着いた環境で学ぶということもそのひとつです。自己について考え、自己を超えた社会を知るなかで、みなさんが今後の人生でなにをなすべきかをぜひみつけてください。社会学はそのためのツールになるはずです。
マエダ ヒロキ
前田 泰樹
教授
社会学科

主な担当科目 保健・医療の社会学
研究テーマ エスノメソドロジーを中心とした質的研究の考え方のもとで、私たちの行為や経験を理解可能にしている「人びどの方法論」を探求しています。現在は、広いいみで医療にかかわるフィールドで、ケアの相互行為や協働実践のあり方や、病いの経験の語りについて、調査研究をしています。
主な業績
『心の文法——医療実践の社会学』(単著)新曜社、2008年
『社会学入門——社会とのかかわり方』(共著)有斐閣、2017年
『概念分析の社会学2——実践の社会的論理』(編著)ナカニシヤ出版、2016年
『概念分析の社会学——社会的経験と人間の科学』(編著)ナカニシヤ出版、2009年
『ワードマップ エスノメソドロジー——人びとの実践から学ぶ』(編著)新曜社、2007年
連絡先 maedahrk@rikkyo.ac.jp
私たちは、日常において、自らや互いの行為や経験を理解しながら社会生活を営んでいます。こうした日常生活の一断片を、はっきりとした輪郭をもった社会的な問題としても理解できるようになることが、社会学の魅力の一つです。社会へのかかわり方(=方法)を身につけ、自らの問いを考えるための力にしてください。
ミワ サトシ
三輪 哲
教授
社会学科
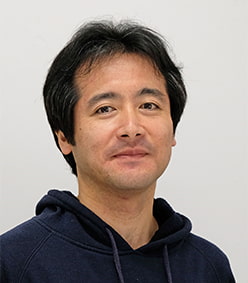
主な担当科目 量的分析法、計量社会学
研究テーマ 計量社会学、データ社会学、階層・階級・移動
主な業績
『日本の社会階層とそのメカニズム』(共著)、白桃社、2011年
『SPSSによる応用多変量解析』(共著)、オーム社、2014年
『少子高齢社会の階層構造1 人生初期の階層構造』(共著)、東京大学出版会、2021年
『基礎から学ぶやさしい心理統計』(監修)、実教出版、2024年
連絡用メールアドレス smiwa@rikkyo.ac,jp
大学時代は、人生のなかで(おそらく)最も自由に時間を使うことができる時期です。勉強するのもよし、遊ぶのもよし、です。ただ実のところ、密かな「特権」は、研究をすることかもしれません。大学の資源(本、データベース、コンピュータソフトなど)を活かし、またその道の専門家の支援を受けて、卒業論文や卒業研究に取り組むのも、はまればきっと楽しい貴重な経験になります。何はともあれ、ここで社会学と向かい合ってみてください。
ヤマモト タカノリ
山本 崇記
教授
社会学科
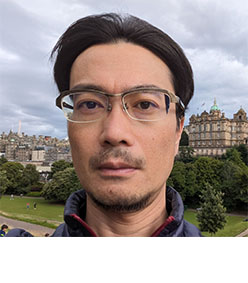
主な担当科目
福祉の社会学、社会運動論
研究テーマ
差別・マイノリティ、都市・地域
主な業績
『住民運動と行政権力のエスノグラフィ—差別と住民主体をめぐる〈京都論〉』(晃洋書房、2020年)
『差別研究の現代的展開—理論・規制・回復をめぐる社会学』(日本評論社、2022年)
「住民運動は持続可能か—マイノリティコミュニティにおける自立と不作為のパラドクス」『現代思想』52(17):189-202 、2024年
連絡先 yamamoto.takanori@rikkyo.ac.jp
「当事者」と出会うこと。同時に自らの〈当事者性〉に現象的・構造的にアプローチすることが、社会学の醍醐味だと思います。学びの「現場」を通じて皆さんとともに歩みたいと思います。
現代文化学科
イシイ カヨコ
石井 香世子
教授
現代文化学科

主な担当科目 国際社会学・エスニシティ論・専門演習など
研究テーマ 現代アジアのグローバリゼーション(移民・観光とエスニック・マイノリティ)
連絡先 ishiik@rikkyo.ac.jp
国際観光の場でエスニック・イメージを売る山地民の人々について研究するうち、気づけば調査対象者がどんどん海外へ移住していたため、移民について研究するようになりました。現在のおもな興味関心は、子どもの移住・移動する子どもたちとエスニシティです。
◆現在の研究課題:
アジアの越境する子どもたち、トランスナショナル階層化
著書や論文:
Marriage Migration in Asia:Emerging Minorities at the Frontiers of Nation-States, Kyoto University Press/National University of Singapore Press 2016年.(編著)
The Impact of Ethnic Tourism on Hill Tribes in Thailand,” Annals of Tourism Research, vol.39 no.1 pp. 290–310. 2012年. (単著)
『異文化接触から見る市民意識とエスニシティの動態』慶應義塾大学出版会. 2007年.(単著)
オオクラ スエヒサ
大倉 季久
教授
現代文化学科

主な担当科目 環境政策論、専門演習など
研究テーマ 経済社会学、環境社会学、サステイナビリティ研究
主な業績
『森のサステイナブル・エコノミー:現代日本の森林問題と経済社会学』(晃洋書房、2017年).
「脱市場社会のサステイナビリティ」(『サステイナビリティ研究』9号、2019年).
「『個人化社会』と農業と環境の持続可能性のゆくえ:クオリティ・ターン以後」(『環境社会学研究』25号、2017年).
連絡先 ohkuras@rikkyo.ac.jp
気候変動やエネルギー転換といった環境政策上の課題の解決は一見、社会学とは隔たりが感じられるテーマだと思いますが、実は社会学のなかでしばしば耳にする「つながり」や「ネットワーク」といった現象と深くかかわるテーマです。環境の危機というと、自分一人ではどうにもならない、とてつもなく大きい問題に聞こえるかもしれません。ですがそう考えてみると、原因や、解決のきっかけは案外身近なところにあるということも見えてくると思います。
オオタ マキコ
太田 麻希子
教授
現代文化学科

主な担当科目 グローバル都市論、専門演習1、専門演習2、基礎演習など
研究テーマ フィリピン、マニラ首都圏の産業及び空間構造の変容下における女性の労働と居住、生活について、同地域のスラムでのフィールドワークや文献資料、統計調査に基づいて研究している。
主な業績
「重層する戦略の場としての住民組織─マニラ首都圏のスクオッター集落住民組織における女性の活動事例から」2009年、『アジア研究』55巻3号
「フィリピン・マニラ首都圏における「スラム」の動態的研究─複合する生産/再生産領域のジェンダー分析」2010年、博士学位論文(お茶の水女子大学大学院人間文化研究科)
「マニラ首都圏のスラムにおける女性住民の生活実践─移動・就労・住民組織─」2011年、『女性学研究』18号
連絡先 ota_mk@rikkyo.ac.jp
大学時代の様々な人やものとの出会いを大切に、自分と他者、自分と世界との関係について思考する力を培ってください。
キムラ ミズカ
木村 自
教授 / 学科長
現代文化学科

主な担当科目 文化人類学、国際社会学、専門演習ほか
専門分野 文化人類学、ディアスポラ論、地域研究(中国、台湾、東南アジア)
研究テーマ (1)中国・台湾におけるエスニック・マイノリティ研究 (2)中国系住民(華僑華人)のディアスポラ空間に関する研究 (3)台湾の視覚障害者文化に関する研究
主な業績
『東南アジア地域研究入門 2 社会』(分担執筆)慶応義塾大学出版会、2017
『雲南ムスリム・ディアスポラの民族誌』(単著)風響社、2016
『グローバリゼーションズ—人類学、歴史学、地域研究の現場から』(分担執筆)弘文堂、2012
『越境とアイデンティフィケーション—国籍・パスポート・IDカード』(分担執筆)新曜社、2012
『実践としてのコミュニティ: 移動・国家・運動』(分担執筆)京都大学出版会、2012
『ディアスポラから世界を読む』(分担執筆)明石書店、2009
連絡先 kimuramizuka@rikkyo.ac.jp
小学校3年生の時、私は両親に連れられて、大阪吹田市にある国立民族学博物館を訪れた。世界中から集められ、館内に溢れる多様なもの、もの、ものに、私はひたすら圧倒された。この時の経験が、私のその後の人生をある程度決めてしまったのだと思う。異文化への憧れから、学部で中国語を専門に学び、そしてその「憧れ」を相対化するために、大学院で文化人類学を学んだ。今たどり着いたのは、文化の「間」から文化を考えること。まだ途上の研究をいつか完成させたい。
◆学生へのメッセージ:
目的地に向かってただひたすら走り続けるのもいいけれど、ときに寄り道し、ときに道に迷いながら未知の光景を彷徨ってみるのも面白い。未知の光景を彷徨い、他者の声に耳を傾けながら、自分のあたりまえがガラガラと音を立てて崩れていく体験が1度でも2度でもできたなら、それで大学生活の4年間は十分に価値あるものだと思う。自戒も込めて一言。寄り道しよう!
コイケ ヤスシ
小池 靖
教授
現代文化学科

主な担当科目 宗教社会学、セラピー文化論
研究テーマ 心理ブームからスピリチュアルまで
主な業績
2018,「心理宗教テクニックと現代日本社会」西村明編『隠される宗教,顕れる宗教』岩波書店, 221-239.
2007,『セラピー文化の社会学』勁草書房.
2002,「現代宗教社会学の論争をめぐるノート-霊性・合理的選択理論・世俗化」『現代宗教2002』東京堂出版, 302-319.
連絡先 koike-toiawase@rikkyo.ac.jp
世の中のアヤシイものから深遠な思想まで扱える「宗教社会学」は、きっと新しい発見への手がかりとなることでしょう。
コイズミ モトヒロ
小泉 元宏
教授
現代文化学科

主な担当科目 アートの社会学、現代文化論、Global Study Programなど
研究テーマ 専門分野は、芸術・文化の社会学、文化政策研究です。アート(arts, 音楽・美術・映画など)や創造性(creativity)と、人々の関係性、地域社会、都市、国家、グローバル社会の形成との関係について研究しています。以下のようなテーマに関心があります。(1)まちづくり・コミュニティとアート、(2)政治・エコノミー・メディアと人々の創造性の関係、(3)サブカルチャーとマイノリティ文化、(4)表現活動を通じた新しいライフスタイル、など。
連絡先 koizumi@rikkyo.ac.jp
Koizumi, Motohiro. 2018. “Connecting with Society and People through ‘Art Projects’ in an Era of Personalization.” In Cities in Asia by and for the People, edited by Yves Cabannes, Mike Douglass, and Rita Padawangi, Amsterdam: Amsterdam University Press.
Koizumi, Motohiro. 2019. “Governance with a Creative Citizenry: Art Projects for Convivial Society in Japanese Cities.” In The Rise of Progressive Cities East and West, edited by Mike Douglass, Romain Garbaye, and Kong-Chong Ho, Singapore: Springer.
野田邦弘, 小泉元宏, 竹内潔, 家中茂. 2020. 『アートがひらく地域のこれから: クリエイティビティを生かす社会へ』ミネルヴァ書房.
◆学生へのメッセージ:
現在、世界はさまざまな危機に直面しています。例えば、人間と環境の関係や、経済・政治活動のあり方の問い直しを迫っている、現下の自然災害やパンデミックの頻発は、今後さらに深刻化しうることも予想されています。このようななかで私たちは、危機を乗り越えられるグローバル社会をいかに築くことができるでしょうか。
私は、人々の多様な創造性を生かし、掛け合わせることが、このような危機を乗り越えていくために重要だと考えています。そして一見すると芸術や文化は、世界の危機的状況とは無縁のようですが、人々の多様な生やライフスタイルを確保し、拡げていくこと、そして、それによって新しい発想や、考え方を生み出していくために欠かすことができない領域です。(危機を乗り越えていくために必要とされる)多角的な物事への見方をもっともよく示す領域の一つが、芸術や文化の領域だ、とも言い換えられるかもしれません。
このようなグローバルな課題や、中・長期的な人間のあり方・社会活動も視野に入れながら、多様な視点に支えられた社会形成を図っていくために、芸術や文化、あるいは人々の多様な創造性が果たしうる役割や実践の可能性、制度的課題について一緒に考えていきましょう。
サダカネ ヒデユキ
貞包 英之
教授
現代文化学科

主な担当科目 消費社会論、現代文化論、専門演習1・2など
専門分野 消費社会論 歴史社会学 現代社会論
主な業績
『消費は誘惑する 遊廓・白米・変化朝顔:一八、一九世紀日本の歴史社会学』(青土社、2015年)
『地方都市を考える:消費社会の先端から』 ( 花伝社、2015年)
『自殺の歴史社会学:意志のゆくえ』(元森絵里子、野上元との共著、青弓社、2016年)
連絡先 hidesadakane@rikkyo.ac.jp
わたしたちは良かれ悪しかれ、商品を買うことで暮らしています。食品やファッション、住居、または教育や介護、保険など。そうして消費を避けがたい要素とする社会はいかに生まれ、育ち、いかなる問題を抱えているのでしょうか。そうした問題関心から、18、19世紀に遡る園芸文化や性的商品に関わる歴史社会学、加えて現代社会における保険や住居、マンガやアニメなどの大衆文化の研究、またそれらが展開される場としての地方都市を中心とする消費環境の調査・分析を進めています。
セキ レイコ
関 礼子
教授
現代文化学科
タカギ コウイチ
高木 恒一
教授
現代文化学科

主な担当科目 都市社会論 他
主な業績
『多層性とダイナミズム——沖縄・石垣島の社会学』東信堂、2018年(共編著)
『都市社会構造論』放送大学教育振興会、2018年(分担執筆)
『はじまりの社会学——問いつづけるためのレッスン』ミネルヴァ書房、2018年(分担執筆)
『都市社会学・入門』有斐閣、2014年(分担執筆)
『都市住宅政策と社会−空間構造:東京圏を事例として』立教大学出版会、2012年(単著)
連絡先 takagi@rikkyo.ac.jp
チェ ファン
崔 煌
助教
現代文化学科

主な担当科目 社会調査法1、社会調査法3、情報処理(入門)、現代社会研究B、基礎演習
研究テーマ 老年社会学、地域社会学
主な業績
①崔煌、権藤恭之、増井幸恵、中川威、安元佐織、小野口航、池邉一典、神出計、樺山舞、2021、「高齢者における社会参加、ソーシャル・キャピタル、主観的幸福感の関連」『老年社会科学』43(1):5-14.
②崔煌、2022、「高齢者の地縁組織への参加と寄付活動、主観的幸福感の関係」『ノンプロフィット・レビュー』22(1):25-32.
連絡先 h.choe@rikkyo.ac.jp
私は高齢者と地域社会の関係について研究しています。皆さんとともに人口高齢化に対する社会のこれからのあり方について考えていきたいと思います。
ミズカミ テツオ
水上 徹男
教授
現代文化学科

主な担当科目 「グローバル社会論」
研究テーマ マイグレーション論、エスニシティなど
連絡先 tetsuo@rikkyo.ac.jp
国際的な人の移動とエスニック・コミュニティの変容などが主な研究テーマです。エスニック人口の増加に伴う社会の変化、政策的な変化なども扱ってきました。これまではオーストラリアのフィールドを中心に活動していましたが、近年はバングラデシュで、日本からの帰還移民を対象とした調査や東京都内のエスニック・タウンでのフィールドワークも実施しています。
◆著書:
『移民政策と多文化コミュニティへの道のり—APFSの外国人住民支援活動の軌跡—』(共編著)現代人文社, 2018.
Creating Social Cohesion in an Interdependent World: Experiences of Australia and Japan.(共編著) Palgrave Macmillan, 2016.
『市民が提案するこれからの移民政策—NPO法人APFSの活動と世界の動向から—』(共編著)現代人文社, 2015.
『トランスナショナリズム』(共訳)(Vertovec, Steven. 2009. Transnationalism (Key Ideas). Routledge)日本評論社, 2014.
The Sojourner Community: Japanese migration and residency in Australia. Leiden: Brill. 2007.
『エスニシティ・人種・ナショナリティのゆくえ』(共訳)(Wallace, Walter L. 1997. Future of Ethnicity, Race, and Nationality. Westport, CT: Praeger)ミネルヴァ書房2003.
リ ウェンウェン
Li Wenwen
助教
現代文化学科

主な担当科目 社会調査法3 現代社会研究F 専門演習1 基礎演習
研究テーマ 家族社会学
主な業績
李ウェンウェン,2022,「異質な近代化:EASS 2016 による日本と中国の配偶者選択の分析」『立命館産業社会論集』 58(3):123-134.
Li, W. and J. Tsutsui, 2021, “Gender Differences in Intergenerational Relationships in Contemporary Urban China,” Japanese Journal of Family Sociology, 33(2): 157-170.
連絡用メールアドレス liwenwen@rikkyo.ac.jp
あたりまえなことがなんであたりまえなこと、おかしなことはなんでおかしなこと、常識から一歩引いて、私たちの社会で起きているあらゆることに対して常に問い直す姿勢を保ち、常識を手放すことを楽しんでいきましょう。心柔らかな自由自在な人間になりましょう。
リリアナ・モライス
Liliana Morais
特任准教授
現代文化学科

担当科目 Japanese Society and Culture, Lecture & Discussion on Social Issues, Global Study Program (Sydney)
研究テーマ art/ craft/ material culture, international migration, transculturalism
主な業績
"Spicing up a 150-year-old porcelain factory: Art, Localism and Transnationalism in Arita's Happy Lucky Kiln", International Journal of Japanese Sociology (日本社会学会), 29第1号 (2019年3月), pp. 52-73.
Cerâmica em Cunha: 40 anos de forno noborigama no Brasil [Cunha Ceramics: 40 years of noborigama kiln in Brazil]. Cunha: Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha, 2016.
"Two Japanese women ceramists in Brazil: identity, culture and representation", Journal of International and Advanced Japanese Studies (筑波大学), 7第 (2015年3月), pp. 201-212.
連絡用メールアドレス liliana.morais@rikkyo.ac.jp
メディア社会学科
イカワ ミツオ
井川 充雄
教授
メディア社会学科

専門分野 メディア社会学、マス・コミュニケーション論、メディア史、地域メディア論
研究テーマ 戦後日本のマス・メディアの変容について、特にメディア・イベント、世論調査や科学コミュニケーションの視点から観察を行っている。
連絡先 m-ikawa@rikkyo.ac.jp
日本のマス・メディアの営為を実証的に明らかにすることにより、その社会的・政治的・文化的変容を歴史社会学的に解明することを研究テーマとしてきた。これまでは、とくに占領期におけるGHQのメディア政策を中心として、戦後のメディア・システムの構築のあり方に関する研究を行ってきた。近年は、メディア・イベント、世論調査、プロパガンダ、科学コミュニケーションといった観点から、戦後日本における世論や社会意識の形においてマス・メディアが果たしてきた役割について考察を行っている。
◆学生へのメッセージ:
我々が当たり前と思って普段見すごしていることに、目を向けてみましょう。例えば、人は歩くとき、いちいち「右足を出して、次は左足を出して・・・」などとは考えません。しかし、それに注目することから医学やロボット工学の研究が始まります。それと同様に、日常的に使っている新聞・テレビ・電話等々のメディアやコミュニケーションに、子どものような素朴な疑問の目を向けてみましょう。そこから、学問の第一歩が始まります。
イデグチ アキノリ
井手口 彰典
教授
メディア社会学科

主な担当科目 音楽社会学
研究テーマ 現代社会と音楽との関わりについて。もともと人文学系の「音楽学」を学んでいたのですが、音楽を取り巻く社会の側に興味を惹かれるようになり、気付けばいつのまにか社会学の研究者になっていました。今でも学問の区分にはあまり拘泥せず、領域横断的に文化と向き合っています。
主な業績 『ネットワーク・ミュージッキング』(勁草書房・2009年)、『同人音楽とその周辺』(青弓社・2012年)、『童謡の百年』(筑摩書房・2018年)など。
連絡先 ideguchi@rikkyo.ac.jp
目の前にある色々な事物にただ真正面から向き合うばかりでなく(もちろんそれも大切なことではあるのですが)、一歩退いて「斜めから見る」技術をぜひ身につけてください。少し視点をずらすだけで浮かび上がってくる「何だかヘンなこと=研究の種」が、社会のなかにはたくさん転がっています。
カワハタ ヤスコ
川畑 泰子
准教授
メディア社会学科

主な担当科目 Webスタディーズ, Webスタディー研究, 演習(修士課程)
研究テーマ デジタルアーカイブス(図書館情報学)
主な業績
[1]川畑泰子 "メディアにおける意見形成の解析手法のケーススタディ."社会情報学第8巻2号 (2019), pp.47-64.
[2]Yasuko Kawahata "Analyzing Urban Resilience Using Temporal and Spatial Archive Information Before and After a Disaster–Perspective of SDGs." Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems. Springer, Cham(2019), pp.183-193.
[3]Yasuko Kawahata "Examination of Analysis Method of Opinion Distribution in News Media Transferred on Web. "Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems. Springer, Cham(2019), pp.156-166.
連絡先 kawahata@rikkyo.ac.jp
日常に溢れる多様な情報は時空間制約を超え、デジタルアーカイブスをはじめ、計算機及びネットワークを基盤として可視化が出来つつあります。 それによりこれまで未開拓であった歴史や普遍性のある現象との繋がりなども理解がしやすくなりつつあります。私たちの社会生活を構成しうるメディアの変遷とそれらを取り巻く情報媒体の変化を多様な分析アプローチを学びつつ、考察・分析を共にできればと思います。
キノシタ コウイチ
木下 浩一
特任准教授
メディア社会学科

主な担当科目
メディア社会特講4
社会学特殊研究A
研究テーマ
メディアやジャーナリズムの送り手研究
・新聞記者のルーチン(現在進行中)
・テレビのワイドショーやクイズ番組
・吹き替えや声優
(次の分析対象は、通信社の記者や通信士?)
主な業績
単著『新聞記者とニュースルーム:一五〇年の闘いと、妥協』新聞通信調査会、2024年.
単著『テレビから学んだ時代:商業教育局のクイズ・洋画・ニュースショー』世界思想社、2021年.
単著『やりたい事が無い人こそホワイトへ行こう:文系の「学び」と就活』学術研究出版、2025年.
連絡先 kinoshita_koichi@rikkyo.ac.jp
大学時代は、悩み多き時期です。何かと悩むと思います。「ポジティブシンキング」に代表されるように、昨今ネガティブは嫌われます。世の中は、ポジティブな言説で溢れています。
でも本当のポジティブは、ネガティブなことから目を背けません。むしろネガティブなものを直視し、逃げないのが本当のポジティブです。大いに悩んでください。
もしかしたらアナタの悩みは、研究の「芽」かもしれません。社会学はネガティブと親和性が高いのです。立教のキャンパスはキラキラしていますが、外在する社会には問題が山積しています。
悩みを心に抱えながらメディアに接しましょう。一番は、本です。今のところ、本に優るものはありません。
素晴らしい本は沢山ありますが、できれば立教大学の先生が書いた本を手にとってください。本の著者に毎週会ってコミュニケーションが取れるのは、極めて貴重な機会です。特に学術書の著者に接するのは、大学時代だけでしょう。
学びの原初は、アナタが持っている悩みや疑問や懐疑にあります。人や社会に対する興味関心といっていいでしょう。
興味関心を胸に、授業やゼミでお会いしましょう。
◆高校生へのメッセージ:
受験勉強は大変だと思いますが、頑張ってください。立教大学は素晴らしい大学です。頑張るだけの価値があります。春のキャンパスで会いましょう。
キムラ タダマサ
木村 忠正
教授
メディア社会学科

主な担当科目 メディア・コミュニケーション論、専門演習2A・2B
専門分野 メディア・コミュニケーション論、ネットワーク社会論
研究テーマ デジタルネイティブ、ネット世論(炎上、フェイク)、ソーシャルメディアを中心とするメディア・コミュニケーション、スマホ依存、グローバリゼーションに伴う世界システムの変容と日本社会の方向性を中心としたネットワーク社会論研究
主な業績 『ハイブリッド・エスノグラフィー』(新曜社、2018)『デジタルネイティブの時代』(平凡社、2012) 『デジタルデバイドとは何か』(岩波書店、2001) Keitai, Blog, and Kuuki-wo-yomu(EPIC、Vol.2010)
連絡先 kiitostokyo@yahoo.co.jp
もともと文化人類学者として専門教育を受け、「認知人類学」という専門分野で、認知、言葉、コミュニケーション、文化に関心がありました。1990年代半ばから、インターネットの可能性に魅せられ、ネットワークメディア、コミュニケーション、社会文化との関係について探究するようになりました。文化人類学、社会学のもつ多様な観点を活かし、グローバルな政治経済システムの変化といったマクロの視点と、対人コミュニケーションの変化といったミクロの視点を共に大切にしながら、研究テーマに示したようなトピックに多面的、複合的に取り組んでいます。
◆学生へのメッセージ:
21世紀の世界は、これまで以上に、流動的、変動的となり、個々人にとって、大きな可能性が開かれるとともに、リスクもまた社会に広く、深く遍在し、個人に襲いかかります。本学での大学生活を通して、皆さん一人一人が、自らを高め、社会の各界で活躍できる強靱かつ柔軟な能力を身につけることをサポートしていきたいと思っています。
コレナガ ロン
是永 論
教授
メディア社会学科

主な担当科目 社会調査法
研究テーマ メディア・コミュニケーションのエスノメソドロジー、メディアの利用に関する数量的・定性的研究
主な業績
『見ること・聞くことのデザイン』(単著・新曜社)
『モビリティーズのまなざし(共編著・丸善出版)』
連絡先 ronkore@rikkyo.ac.jp
専攻は情報行動論で、人々がメディアを使ってどのようなことを社会的に行なっているのか、ということについて実証的に考えるものです。当初はいわゆる量的な調査といって、普及率や普及要因の分析などをアンケート調査で行なっていました。そのうち、より実態的なものに近づきたいということで、次第にメディアの言説や、相互的な行為の成り立ちといったものにアプローチする方向に移りました。そのため、近年はエスノメソドロジーという質的な方法に基づいた研究について模索しています。
◆学生へのメッセージ:
自分が勉強・研究していた当時の大学と、いまの大学が一番異なるのは、時間の制約の大きさのように思います。時間のマネジメントは大事ですし、それだけ大変かとは思いますが、学校(school)の語源が「暇」であることにいま一度思いをめぐらし、いろいろな問題意識や知識をつなげていくための「すき間」をできるだけ確保するようにつとめてください。
スガモリ アサコ
菅森 朝子
助教
メディア社会学科

主な担当科目 社会学原論2、基礎演習、フィールドスタディーズ
研究テーマ 医療社会学、ジェンダー研究
主な業績
菅森朝子,2019,「乳がん再発をめぐる同病者の「共同性」」,『保健医療社会学論集』,29(2)54-63.
菅森朝子,2017,「乳房再建は何をもたらすのか:乳房再建経験者の語りから」,立教大学ジェンダーフォーラム年報,(19)71-84.
連絡先 asugamori@rikkyo.ac.jp
社会学の調査で学生の立場だからこそ、問えること、出会える人、聞ける話があると思います。さまざまな立場にある人に出会って関わることを大切にしてください。社会学を学んだことは、卒業してからもさまざまな形であなたの「力」になってくれるはずです。
スナカワ ヒロヨシ
砂川 浩慶
教授 / 学部長
メディア社会学科

専門分野 メディア論、放送制度論、放送産業論、ジャーナリズム論
研究テーマ 放送を中心とした制度・政策論、ジャーナリズム、コンテンツ流通
連絡先 sunakawa@rikkyo.ac.jp
放送局の業界団体で20年間、放送制度、著作権、地上デジタル放送などを担当し、2006年度から専任の教員となった。そのような実務経験を活かし、情報通信制度、知的財産制度、ジャーナリズム論、メディア論などを研究していきたい。
◆学生へのメッセージ:
メディア企業を問わず、社会において必要とされる人材は「自分で考え行動できる人」。そのためには自らの仮説を持ち、調査・取材を通して、その仮説を検証し、再構築する探究心旺盛で柔軟な思考と幅広い知識が求められる。大学という器を十二分に活用し、自分の引き出しを沢山作ってください。
ナガサカ トシナリ
長坂 俊成
教授
メディア社会学科

専門分野 防災危機管理論、災害情報論、リスクガバナンス論、リスクコミュニケーション論、社会プロデュース論
連絡先 nagasakaあrikkyo.ac.jp(「あ」を「@」に置き換える)
リスクガバナンスの視点から不確実性を孕むリスクの社会的な協治のための社会システム研究。3.11の教訓を踏まえ分散相互運用環境に対応する官民協働危機管理クラウドシステムに関する研究開発。協働型市民社会を支えるソーシャルメディアとしてのeコミュニティプラットフォームに関する研究開発。リスクコミュニケーションやデジタルアーカイブス、地域プロデュース等、社会制度と情報技術を統合する社会情報学に関する研究に取り組んでいる。
◆これまでの研究生活:
テレワークやSOHO等知識社会における新たなワークスタイルや社会的起業、電子的市民参加、市民の知と専門知を統合する参加型の政策形成、コミュニティの自治、自然災害や高レベル放射性廃棄物などの高度技術社会のリスクガバナンスを支えるリスクコミュニケーションに関する社会実験を通じた実証的な研究に取り組んできた。
◆学生へのメッセージ:
成熟化・複雑化した現代社会は、領域毎の知や個々の要素技術が高度化しながらも、社会の本質的な課題解決に結びつきにくいという矛盾と脆弱性を孕んでいる。こうした閉塞状況を打破し安全・安心な社会を構築するためには、領域横断的に知識や技術を統合し多様な協働性を再編する「リスクガバナンス」の発想を身に付けて、社会的なミッションを達成するプロデューサー型人材が求められている。
ハシモト アキラ
橋本 晃
教授
メディア社会学科

専門分野 ジャーナリズム研究、ジャーナリズム史、米欧ジャーナリズム思想
研究テーマ 19世紀米国ジャーナリズムにおける「プレスの独立」理念の生成過程、19~20世紀フランスジャーナリズムにおける主体の変容
連絡先 ahashimoto@rikkyo.ac.jp
パリ特派員など新聞社記者、米国ジャーナリズム大学院での学修などを経て、今世紀初め、大学教員に。自らの体験も踏まえて、米国がその領土外で行う「限定戦争時のメディア統制とプロパガンダ」の問題を研究してきたが、2006年春に『国際紛争のメディア学』(青弓社)を上梓。以降は、ジャーナリズムに内在しうる権力性、エンタテインメント性などをその始原に遡って検証する、米国ジャーナリズム思想の歴史的研究にシフトした。博士課程は政治学研究科。政治(権力)、人々(公衆?大衆?オーディエンス)とのせめぎ合いの中で紡ぎ出されてきた、今なお紡ぎ出しつつあるジャーナリズム・イデオロギーの解剖学に従事している。
◆学生へのメッセージ:
閉塞感高まるこの国の狭い文脈に押し流されることなく、世界の現実を、自身の頭と眼、足を使って生きてください。大学時代は政治、経済、歴史、哲学、文学、メディアなどの諸学をじっくりと学べるまたとない時期ですが、座学にとどまらず、自らの歩行の一歩一歩が<世界>への接近となるような充実した日々であることを望みます。皆さんがそれを実現するための助力は惜しみません。
ファン ソンビン
黄 盛彬
教授
メディア社会学科

主な担当科目 グローバル・コミュニケーション論、ニュースの社会学1(英語)、質的メデイア研究
研究テーマ メディア・文化研究、グローバルコミュニケーション論、ニュースと世論、ナショナリズムと歴史・他者認識
主な業績
「本音と建前が錯綜する中国人観光客へのまなざし」金成玟・岡本亮輔・周倩編著『東アジア観光学:まなざし・場所・集団』亜紀書房, 2017, pp.242-276.
「戦後日本における『新韓』の意味」『応用社会学研究』(立教大学社会学部)、第59号, pp. 1-23(2017年3月発行)
『韓流のうちそと』徐勝・黄盛彬・庵逧由香共編著、御茶の水書房、2007年、pp. 75-97、pp. 251-287
連絡先 seongbin@rikkyo.ac.jp
韓国の延世大学大学院在学中に立教大学へ交換留学生として派遣されました。立教での大学院時代には、勉強の傍ら、NHKで多くのことを学びました。国際局の韓国語放送のアナウンサーとして、毎週二日程度は渋谷のNHKセンターに通い、毎回の定時ニュースの原稿を翻訳し、韓国語で読むというニュースのアナウンスの仕事やそのほかのパッケージ番組ではインタビューやナレーションなども経験できました。こうしたニュースの現場での経験、そして何より日本のニュースを韓国語で「翻訳し伝える」経験は、現在の私の問題関心の多くを形成しているように思われます。2000年からは、京都の立命館大学で教え、2007年に立教に戻りましたが、日本の東西を往復した経験、そして、また在外研究を行った米国・西海岸での経験から、民族や歴史といったナショナリズムの源泉となりがちな考え方が、そもそも本質的なものではなく、変わりうる「立ち位置」の問題であることを実感させてくれました。そして、この越境空間に住んでいる我々が、どのように過去や現実と向き合うかを考えています。
リン イーシェン
林 怡蕿
教授 / 学科長
メディア社会学科

専門分野 社会情報学、マスメディア研究、ジャーナリズム研究
研究テーマ エスニック・メディア研究、オルターナティブ・メディア研究、マスメディア制度とジャーナリズム活動の相互関連の研究
連絡先 lin@rikkyo.ac.jp
社会運動、公共圏、多文化主義などの理論概念を用いて、現代におけるマスメディアの機能的・構造的欠陥を把握しつつ、エスニック・メディアやオルターナティブ・メディアの可能性について実証的、理論的に研究している。ケースとして台湾のエスニック・メディアと放送制度のあり方について研究し、博士論文を書いた。東アジアにおける放送産業構造の変容とジャーナリズムのプロフェッションとの関連について国際比較研究にもたずさわってきた。近年は特にメディア言説における「他者」の表象問題に取り組んでいる。ケースとしては、華僑・華人などのディアスポラとメディアとの関わりに注目し、華僑・華人社会における文化や言語、アイデンティティの形成と変容を中心に研究している。また、「当事者」に着目する視点から東日本大震災の関連記事の内容分析や、被災地の多言語放送活動を通して外国人住民との地域共生の課題を考察している。
◆学生へのメッセージ:
大学はディズニーランドのようだと思います。安いとは言えない入場料(=授業料)を払ってゲートをくぐったら、あとは限られた時間のなかでどれだけのアトラクション(=授業、部活、調査活動)を楽しめるか…ですが、これはもう個人の勝負です。ただベンチに座って周りを眺めて時間を潰すか。それともファストパスを片手にできるだけ多くのアトラクションに入場して、自分を成長させていくか。どのようにして入場料以上の価値を得るかは自分の努力次第です。退園前に、夜空に広がる大きな花火を見上げながら「来てよかった、楽しかった」と言えるように、悔いのない大学生活を送ってください。
ワダ シンイチロウ
和田 伸一郎
教授
メディア社会学科

主な担当科目 情報社会論
研究テーマ 情報社会論、AI社会論、社会思想、自然言語処理
主な業績
「Python, Embedding Projector を用いたTwitterデータ分析 : 2016年東京都知事選挙を事例に」(『応用社会学研究 』( 61 ) 、立教大学社会学部、2019年)
「『新デジタル時代』と新しい資本主義」 (『岩波講座現代〈第9巻〉デジタル情報社会の未来 9巻』、岩波書店、2016年)
『国家とインターネット』 (講談社選書メチエ、2013(電子版2015))
連絡先 wadakqs@rikkyo.ac.jp
現代哲学(「存在論」)からメディア論へアプローチすることから始まり、続いて「倫理」からそれへアプローチした後、クラウド・コンピューティングの普及(コンピューティングのカジュアル化)という新デジタル時代に入ったところで、その環境下における民衆の視線から「デモクラシー」とは何かを問い直し、さらにその後、国際政治とグローバル市場経済の観点から、インターネットとは何かを問うてきた。「理論」、「概念」を通じてしか到達できない洞察というものがあること、まさにそれゆえに、それらに固有の有効性があるということ、を提示することに努めている。
◆学生へのメッセージ:
今後、世界的潮流の中で、日本社会も「働き方改革」、デジタル・トランスフォーメーション(DX)、人工知能の社会実装などを通して、既存の在り方から、いわゆる「Society5.0/超スマート社会」へと変わっていき、10年、20年先、劇的に変化を遂げているでしょう。そうすると、その社会ではどういう人が求められるのか、そこから逆算して、いま自分に必要なスキル、知性、教養とは何かを考えて、主体的に自分なりの学びと人生を設計する意識をもつことが重要になってきます。そういったメディア社会学科生になってくれるとうれしいです。

