ゼミ紹介社会学科
働くことは生きることです。どう働くかは、どう生きるかにつながることです。李ゼミは、働くことの研究を通じて、生きることや社会の仕組みについて考えるゼミです。
近年、フレキシブルかつ自由な働き方、仕事における自律、企業から自立した仕事人、仕事の趣味化、などのフレーズをよく聞きます。これらのフレーズはここ20数年間仕事の世界で起こっている諸変化を部分的には表しています。
ゼミでは、労働・仕事・雇用システムにおける近年のドラマティックな変化について考察した上、「ワークシステムの変化の下で労働者は主体的に働けるか」、「サービス労働における労働のルーティン化や感情労働の企業による管理は労働者のアイデンティティにどのような影響を与えるか」、「なぜ労働者は長時間労働するか」、「ワークとライフのバランスの取れた働き方をするためにはどんな政策が必要なのか」、「職場で労働者はどのようにジェンダーをやっているか」など、労働社会学の長年のイッシューはもちろん現在のホットなイッシューを取り上げ、議論します。
ゼミでは、議論にとどまらず、実際企業や労働者に対しアンケートやインタビューを実施し、議論と調査を結びつける作業を行います。現在新自由主義の弊害として議論されている「格差社会」も、実は仕事世界の変化の結果でもあります。ゼミの皆さんには、仕事についての考察を通じて、仕事の意味や社会の仕組みを知ってもらいたいと思います。
近年、フレキシブルかつ自由な働き方、仕事における自律、企業から自立した仕事人、仕事の趣味化、などのフレーズをよく聞きます。これらのフレーズはここ20数年間仕事の世界で起こっている諸変化を部分的には表しています。
ゼミでは、労働・仕事・雇用システムにおける近年のドラマティックな変化について考察した上、「ワークシステムの変化の下で労働者は主体的に働けるか」、「サービス労働における労働のルーティン化や感情労働の企業による管理は労働者のアイデンティティにどのような影響を与えるか」、「なぜ労働者は長時間労働するか」、「ワークとライフのバランスの取れた働き方をするためにはどんな政策が必要なのか」、「職場で労働者はどのようにジェンダーをやっているか」など、労働社会学の長年のイッシューはもちろん現在のホットなイッシューを取り上げ、議論します。
ゼミでは、議論にとどまらず、実際企業や労働者に対しアンケートやインタビューを実施し、議論と調査を結びつける作業を行います。現在新自由主義の弊害として議論されている「格差社会」も、実は仕事世界の変化の結果でもあります。ゼミの皆さんには、仕事についての考察を通じて、仕事の意味や社会の仕組みを知ってもらいたいと思います。
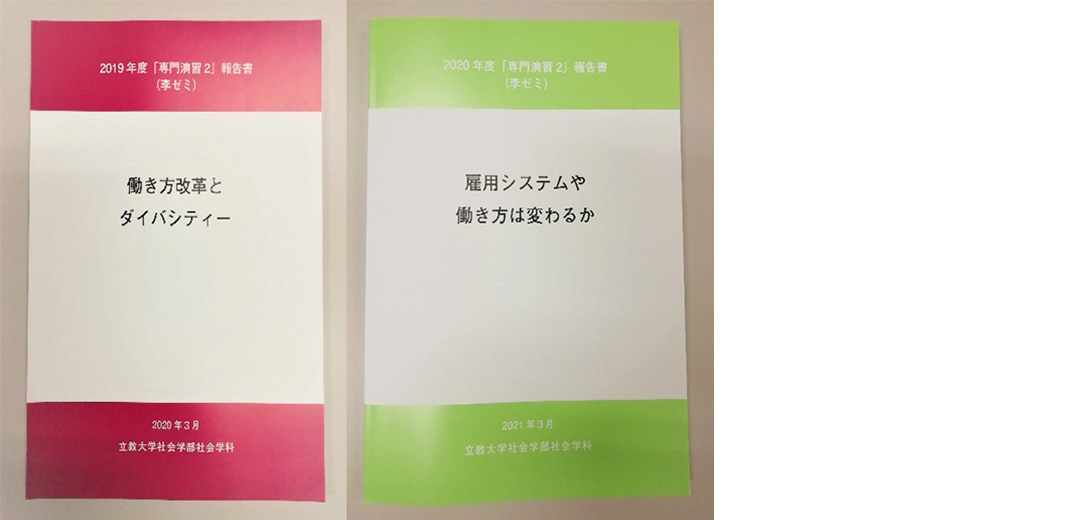
2019年度は、近年盛んに議論されている「働き方改革」と女性や高齢者、外国人労働者、障がい者など様々な人材の多様な働き方について研究しました。研究の成果として、『働き方改革とダイバシティ—』という報告書を刊行しました。
2020年度は、コロナ過でゼミ生たちはゼミ研究をするにあたって対面インタビューができないなど困難もあったが、日本型雇用システムの持続と変化、ICTやAIと働き方の変化、女性の就業パターンの変化などについて研究し、『雇用システムや働き方は変わるか』という報告書を刊行しました。
2020年度は、コロナ過でゼミ生たちはゼミ研究をするにあたって対面インタビューができないなど困難もあったが、日本型雇用システムの持続と変化、ICTやAIと働き方の変化、女性の就業パターンの変化などについて研究し、『雇用システムや働き方は変わるか』という報告書を刊行しました。
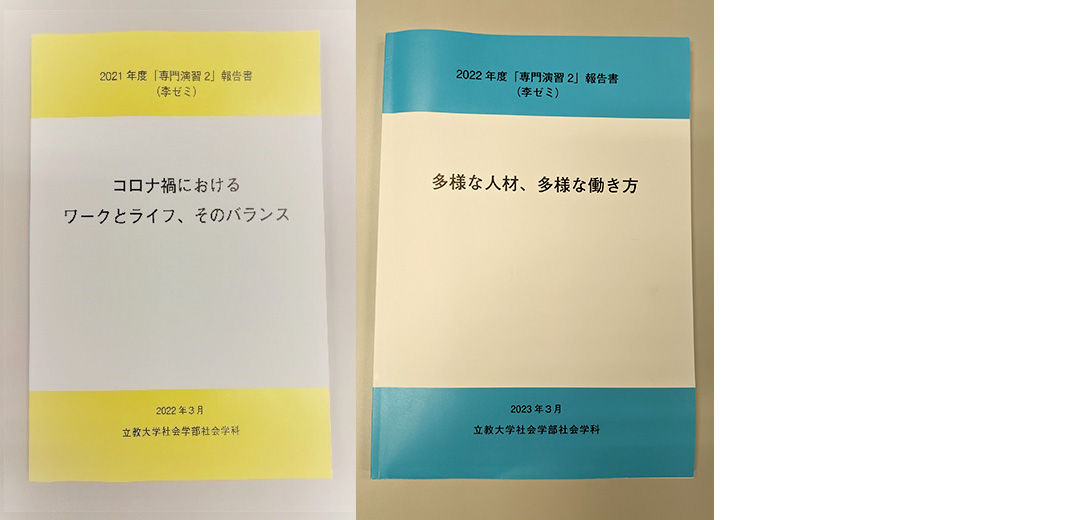
2021年度は、コロナ禍でワークとライフに起こった変化、情報化・知識経済化時代への労働者や企業の対応、女性の活躍と継続就業、外国人労働者の就労やライフなどについて研究し、『コロナ禍におけるワークとライフ、そのバランス』という報告書を刊行しました。
2022年度は、女性、外国人労働者、性的マイノリティなどの多様な人材の雇用問題やフリーランスなどの多様な働き方に関して研究し、『多様な人材、多様な働き方』という報告書を刊行しました。
2022年度は、女性、外国人労働者、性的マイノリティなどの多様な人材の雇用問題やフリーランスなどの多様な働き方に関して研究し、『多様な人材、多様な働き方』という報告書を刊行しました。
2023年度は、日本人の働く意味や人材マネジメントのダイバーシティなどに関して研究し、『仕事に対する価値観の変化とダイバーシティ』という報告書を刊行しました。
2024年度は、働く人に自主性を与える働き方やワーク・エンゲージメントに関して研究し、『働き方と自主性、ワーク・エンゲージメント』という報告書を刊行しました。
2024年度は、働く人に自主性を与える働き方やワーク・エンゲージメントに関して研究し、『働き方と自主性、ワーク・エンゲージメント』という報告書を刊行しました。
2024年度ゼミ生の一言

4年生とゼミ合宿を終えて(千葉市フォレストビレッジにて、2025.9.17)
口分田 義春
在日外国人について、「労働」という観点から見てみようということでこのゼミに入りました。労働社会学にどんどん興味を持つことができました。
小林 奈夏子
3年ゼミでの学びを通じて、企業や雇用制度の視点だけでなく、出産や育児を取り巻く社会的な課題にも目を向けられるようになり、社会問題に対する視野が広がったと感じています。
鷹野 陽菜
このゼミに入る前から興味があった長時間労働問題、ワークモチベーションの問題について研究することができ、とても学びのある経験となりました。
土屋 晃希
ワーク・ライフ・バランスに関する研究を行いましたが、自身の未来にも関わることでもあり、とても勉強になりました。インタビュー調査は社会人と話すことの難しさはありましたが、いろいろな経験豊富な話を聞くことができて楽しかったです。
藤井 爽
労働社会学に興味を持ったきっかけは、就職活動を本格的に始めるにあたり、自分自身のキャリアを考える中で、労働環境や働き方に関する社会的な課題に関心を抱いたことでした。
鈴木 彩心
労働社会学のゼミに入る前は、労働の仕組みなどについての知識は全くと言っていいほど乏しいものでした。調べを進めているうちに今の日本にとって重要であり、知識が増える度に面白さに気づいていきました。
長井 遥奈
労働に関する社会問題への理解を深めました。自分では思いつかない視点から労働問題を考察する学生もおり、多くの刺激を受けました。
井口 朝陽
ゼミ活動を振り返ってみると、新しい知見をたくさん得ることができたと感じています。様々な観点から労働社会学についての知識を身につけることができたと思います。
梅本 裕貴
仮説を立てるところから苦しみ、先生が最後までアドバイスを惜しまずしてくれたおかげで何とかゼミ論文を完成させることが出来ました。
神山 実咲
三年ゼミを通じて、新たな知見を得ながら、自分の興味に沿った研究ができた意義のある一年でした。
小林 ミカス
三年ゼミの活動を振り返ると、多くの学びと成長があったと思います。自らテーマを設定し、データの収集・分析を進める中で、研究を進める難しさと面白さの両方を実感しました。
齋藤 音々
この1年間でさまざまな文献をもとに、日本の労働環境にはどのような課題があり、どのように解決するべきなのかについて学ぶことができました。
永村 麻衣
既存の研究を整理しながら自分の研究の独自性をどこに見出すかを考える過程は大きな学びになりました。
西沢 周祐
様々な知識やインタビューの作法はもちろん、「物事に直接触れて理解する」ということの重要性など、大切なことを多く学べました。
檜原 健瑠
ほかの講義などではこなすだけになっていたが、ゼミでは課題に対して向き合えたと思います。自分の中で「労働社会学」に対する解像度が高まったことが何よりも大きな事だと思います。
細野 睦貴
労働社会学に関する知見があまりなかった自分にとって、論文作成の難しさを痛感すると同時に自分自身で仮説を設定し調査、考察することの面白みを感じることができました。
在日外国人について、「労働」という観点から見てみようということでこのゼミに入りました。労働社会学にどんどん興味を持つことができました。
小林 奈夏子
3年ゼミでの学びを通じて、企業や雇用制度の視点だけでなく、出産や育児を取り巻く社会的な課題にも目を向けられるようになり、社会問題に対する視野が広がったと感じています。
鷹野 陽菜
このゼミに入る前から興味があった長時間労働問題、ワークモチベーションの問題について研究することができ、とても学びのある経験となりました。
土屋 晃希
ワーク・ライフ・バランスに関する研究を行いましたが、自身の未来にも関わることでもあり、とても勉強になりました。インタビュー調査は社会人と話すことの難しさはありましたが、いろいろな経験豊富な話を聞くことができて楽しかったです。
藤井 爽
労働社会学に興味を持ったきっかけは、就職活動を本格的に始めるにあたり、自分自身のキャリアを考える中で、労働環境や働き方に関する社会的な課題に関心を抱いたことでした。
鈴木 彩心
労働社会学のゼミに入る前は、労働の仕組みなどについての知識は全くと言っていいほど乏しいものでした。調べを進めているうちに今の日本にとって重要であり、知識が増える度に面白さに気づいていきました。
長井 遥奈
労働に関する社会問題への理解を深めました。自分では思いつかない視点から労働問題を考察する学生もおり、多くの刺激を受けました。
井口 朝陽
ゼミ活動を振り返ってみると、新しい知見をたくさん得ることができたと感じています。様々な観点から労働社会学についての知識を身につけることができたと思います。
梅本 裕貴
仮説を立てるところから苦しみ、先生が最後までアドバイスを惜しまずしてくれたおかげで何とかゼミ論文を完成させることが出来ました。
神山 実咲
三年ゼミを通じて、新たな知見を得ながら、自分の興味に沿った研究ができた意義のある一年でした。
小林 ミカス
三年ゼミの活動を振り返ると、多くの学びと成長があったと思います。自らテーマを設定し、データの収集・分析を進める中で、研究を進める難しさと面白さの両方を実感しました。
齋藤 音々
この1年間でさまざまな文献をもとに、日本の労働環境にはどのような課題があり、どのように解決するべきなのかについて学ぶことができました。
永村 麻衣
既存の研究を整理しながら自分の研究の独自性をどこに見出すかを考える過程は大きな学びになりました。
西沢 周祐
様々な知識やインタビューの作法はもちろん、「物事に直接触れて理解する」ということの重要性など、大切なことを多く学べました。
檜原 健瑠
ほかの講義などではこなすだけになっていたが、ゼミでは課題に対して向き合えたと思います。自分の中で「労働社会学」に対する解像度が高まったことが何よりも大きな事だと思います。
細野 睦貴
労働社会学に関する知見があまりなかった自分にとって、論文作成の難しさを痛感すると同時に自分自身で仮説を設定し調査、考察することの面白みを感じることができました。
卒論題目の例
卒論題目
- 組織市民行動-促進する要因と個人が受ける恩恵
- 男性の育児休暇取得が企業にもたらすメリット
- 働き方改革における生産性の向上
- 職業構成の変化からみる地域性の変化
- 接客サービス労働者と顧客の間で観察されるアンバランスな関係
- 男性のワークライフバランス実現は可能か
- 組織におけるリーダーのあり方
- 地方企業における人材獲得課題
- 文系大学時代のキャリア意識や経験が就業後の能力に与える影響
- 介護業界における中核人材の確保
- 現代における性別役割分業意識の特徴とその影響
- 男性の家事育児参加を阻害する要因と参加がもたらすポジティブな側面
- 衣服の外見的メッセージと服装規定の実情
- ブラック企業と労働組合の役割
- 企業における障がい者・LGBTの雇用の現状と施策
- 対人サービス業従事者の感情労働とパーソナリティ
- 組織文化から見つめるテレワークとその存在意義
- 日本型雇用システムの存続—日経225から読み解く今後の動向
- 日本とアメリカの労働に対する考え方の違い
- 男性の在宅勤務と家庭生活満足度の関係性
- 女子学生のキャリア選択に影響を与える要因
- AI技術による技術革新と労働者の共生について
- 接客労働者における感情管理の複雑性と自律性-美容部員を事例に(2021年度社会学科優秀論文賞受賞論文)
- 70歳現役時代における高齢労働者の理想と現実の乖離
- 転勤に対する共働き総合職世帯のキャリアと家庭を両立する戦略-コミューターマリッジに着目してー
- 外国人技能実習生の実態と課題—ベトナム技能実習生を中心に
- コロナ禍は若者の労働意識にどのような変化をもたらしたのか
- テレワーク下における長時間労働の要因と対策
- 男性限定正社員の就労と男性性
- 女性の管理職志向の低さとその改善
- 労働生産性を向上させるオフィスと社員の関係性
- 職場における喫煙者と労働
- 仕事満足度を上げる要因についての考察
- 弾力的労働時間制の導入における課題
- 働きやすさと人間関係、SNS利用の影響について
- 地方における介護士不足に関しての考察
- 小売業に従事する正規労働者と非正規労働者の春闘に対する評価の違い
- 総合職を選択する女子大学生の男性性について
- 早期離職者の離職要因と転職後のキャリア満足度の関係性
- 雇用システムの違いがトランスジェンダーの職場に与える影響について
- 就職活動における早期化、長期化問題とその解決策
- 企業の健康経営が労働者に与える影響
- 今日の大学生の就職意識について
- 教師の感情労働が及ぼす働きがいへの影響について
- 若年労働者の意識とネットワークー現代社会における人間関係とはー
- Uターン・Iターンが若者のキャリア選択に与える影響
- 管理職の仕事と介護の両立
- 専門外国人材の企業への文化的適応
- 親の職業的地位が女子大学生の職業選択に与える影響
- ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンが日本企業に与える好影響
- 就職活動におけるOB・OG訪問の役割変化
- 伝統的仏教寺院における感情労働の実態と比較
- 男性の育児休業が与える影響と考え方の変化
- 若年女性の継続就業意思と会社の女性活躍施策
- 非組合員の労働組合への意識—労働組合の社会的効果を手掛かりにー
- 専業フリーランスと仕事の自律性
- 体育会出身の会社員における労働観
アイデンティティ、コミュニケーション、文化から現代社会を考える
ゼミのテーマ
このゼミでは、アイデンティティ/コミュニケーション/文化といったキーワードを軸に、さまざまな社会現象について理論的視点をふまえたかたちで分析していきます。そういうと堅苦しく聞こえるかもしれませんが、これらのキーワードは、どんな出来事についてもからめることができるものなので、わかりやすくいえば“やりたいことができる”と言いかえることができるかもしれません。みなさんが自分なりの考えたい問題があり、それを「社会学的」に考えたいのであれば、受け止められるテーマ設定であると思います。
ただし、ここで言う“やりたいことができる”ということは“なんでもあり”とはまったく違います。先ほど、「社会学的」という言葉を使いましたが、当然、“やりたいこと”を学問的に意味があるものにするためには、きちんとふまえる手続きがあります。自分が“やりたいこと”を学問的に成り立つものにするためにはどうすればよいか、それを学生と教員のコミュニケーションの中でいろいろと探っていくのがこのゼミの目的です。
ただし、ここで言う“やりたいことができる”ということは“なんでもあり”とはまったく違います。先ほど、「社会学的」という言葉を使いましたが、当然、“やりたいこと”を学問的に意味があるものにするためには、きちんとふまえる手続きがあります。自分が“やりたいこと”を学問的に成り立つものにするためにはどうすればよいか、それを学生と教員のコミュニケーションの中でいろいろと探っていくのがこのゼミの目的です。
ゼミの中で意識していること
そのときに意識してもらいたいのが、他のゼミ生の研究との関係です。ゼミの中にはさまざまな問題関心を持った学生がいますが、自分とは関係がない内容であるとは思わずに、他のメンバー全員の研究内容に興味を持って欲しいなと考えています。誰かが一生懸命に考えている内容はそれだけでおもしろいはずですし、意外なところで、自分の研究内容と重なる部分やヒントとなる部分を発見できると思います。みなが同じ時代の同じ社会の中を生きているわけですから、そこには思わぬつながりがあってもおかしくありません。わたしの専門は理論社会学という抽象的な分野ですが、理論が持つ抽象性は、一見、バラバラに思える内容をつなぐハブ空港のような役割を担えると思っています。真剣に考えた学問内容だからこそ生まれる、濃密なコミュニケーションのおもしろさに気付いてもらえたらうれしいです。そういうコミュニケーションを生み出すための「広場」のようなものをつくるのがこのゼミ担当教員としての仕事ですね。
どんな学生に来て欲しいか
そんなわけで来て欲しい学生はまず「他人に興味がある人」です。人の言うことを真剣に聞いてそのおもしろさをみつけられて、影響をどんどんと受けて自分を変えていける人たちが集まってくれるととても楽しくなると思います。そしてそれを裏返して言えば、自分がなにかを発表するときにも、真剣に他人が聞いていることを意識して、自分の研究をきちんとしたかたちにできる「自分なりの問題関心を持っている人」に来て欲しいということでもあります。他人に興味を持ち、他人に影響を受けることができる人というのは、きちんと自分の中身をつくろうとしている人であるとも言えるでしょう。このゼミのテーマである「アイデンティティ」と「コミュニケーション」の関係についての話でもあります。わたしも、みなさんからの影響をどんどん受けて自分をさらに変えていきたいと思っていますし、また、みなさんにとって刺激的なことを伝えられるように自分の思考を形作っていきたいと思っています。
片上ゼミは、2018年度より新たにはじまったゼミで、まだまだ試行錯誤しながら、たくさんの実験の中でより良い場所をつくっていきたいと思っています。ですから、この実験に楽しみながら積極的に参加してくれる人が来てくれることを望みます!
片上ゼミは、2018年度より新たにはじまったゼミで、まだまだ試行錯誤しながら、たくさんの実験の中でより良い場所をつくっていきたいと思っています。ですから、この実験に楽しみながら積極的に参加してくれる人が来てくれることを望みます!
ジェンダー/セクシュアリティの社会学
ゼミのねらい
「性(ジェンダー/セクシュアリティ)」をめぐる固定観念や規範は、個人の経験や社会のしくみに様々な仕方で影響を与え、ときに特定の社会集団を排除したり、深刻な社会問題を生じさせたりします。「性」について社会学的に学ぶという営みは、格差や差別について学ぶことと不可分です。格差や差別などの不正義のある現状をジェンダー/セクシュアリティの視点から分析する力を身につけることが、このゼミのねらいです。どんな学生に参加してほしいか
現代社会のあり方に対して疑問や憤りのある人。他者の問題(社会の問題)も自分と地続きであると考え、関心を寄せられる人。自分の経験、身の回りで起きた出来事、ニュース報道などをジェンダー/セクシュアリティの視点からとらえ、それによって気づいたことを誰かと話したい人。◎杉浦ゼミは2024年度から始まりました。
教育・階層・就職の問題から社会を斬る
ゼミのテーマ・ゼミを通して学ぶこと
このゼミは、主として教育に関するテーマを取り上げ、そこから今の社会の仕組みを考えることを目的としています。皆さんにとって、学校は非常に身近な存在だと思います。ですから、教育や学校に関する問題は、よく知っている、と思うかもしれません。ただし、ある現象を見聞きしたこと、経験したことも、その見え方、解釈は人によって異なります。学校に関するテーマは、個人の経験に照らして、時には独善的と思える意見を述べる人もいます。しかしその経験は、どの学校にも当てはまるのか、安易に一般化できる話なのか、ということはよく検討されなければいけません。身近に感じる問題だからこそ、対象から距離を取り、客観的に見つめる必要があります。
このゼミは「社会学」を扱うので、あくまで教育に関係する現象を実証的に把握することが重要であり、個人的な教育論や、安直な解決策を提案することは求めていません。もちろん、今学校周辺で起こっている教育問題を解決したい、という志向の人も歓迎します。ただ解決策を提案するには、まず現実を見つめる必要があります。誤った現状認識のもとでは、有効な提案などできるはずがないからです。ですから、何らかのデータや資料など、根拠になり得るものを探し、収集し、そうした証拠(エビデンス)に基づいて議論を展開するという姿勢を、このゼミで学んでほしいと思います。
このゼミは「社会学」を扱うので、あくまで教育に関係する現象を実証的に把握することが重要であり、個人的な教育論や、安直な解決策を提案することは求めていません。もちろん、今学校周辺で起こっている教育問題を解決したい、という志向の人も歓迎します。ただ解決策を提案するには、まず現実を見つめる必要があります。誤った現状認識のもとでは、有効な提案などできるはずがないからです。ですから、何らかのデータや資料など、根拠になり得るものを探し、収集し、そうした証拠(エビデンス)に基づいて議論を展開するという姿勢を、このゼミで学んでほしいと思います。
ゼミの進め方
専門演習2は、メンバーをグループに分けて、グループごとにレジュメを準備し、課題文献について発表し、ディスカッションを行います。前期は教育社会学のテキストを用いて、教育社会学のテーマを網羅的に取り扱います。その中で、徐々に自分の卒論のテーマを絞り込んでください。後期になると、教育に関係するテーマをもとに、ディベートを実施します。その準備に、グループごとの調べ学習が必要となってきます。なお、現在COVID-19の問題があり実現は困難ですが、感染症の問題が解決されれば、合宿などを行うことも考えています。
◎このゼミは2020年度から始まりました。卒論については、方法論は問わないので、何らかの調査を行う、あるいは何らかのデータや資料を自分で集めて、それに基づいて議論を組み立てることを学生には期待しています。
◎このゼミは2020年度から始まりました。卒論については、方法論は問わないので、何らかの調査を行う、あるいは何らかのデータや資料を自分で集めて、それに基づいて議論を組み立てることを学生には期待しています。
コミュニティ再生!それは「共生」から始まる

2015西山ゼミの風景
みなさんの暮らす地域社会(コミュニティ)では、中心市街地の衰退、限界集落による過疎問題、路上生活者の増加、など様々な社会問題が発生しています。こうした問題を誰が、どのように解決しているのでしょうか?西山ゼミは、身近なところに存在しているが、あまり注目することの少ないコミュニティの研究を通して、社会のしくみや生き方の方向性を考えていきます。
近年、政府や行政、企業だけでなく、ボランティアやNPO/NGOなどの市民活動団体が公共サービスの担い手として注目されています。これらの組織は、自発的に柔軟に問題を発見し、その解決に取り組んでいます。とりわけまちづくりやコミュニティ形成に対しては、行政と企業、市民が協力するパートナーシップ(協働)の役割分担について考えていく必要性が高まっています。ゼミの大きなテーマは、まちづくり、市民活動の展開、行政との協働、都市政策など、コミュニティで発生する問題を幅広く扱います。
近年、政府や行政、企業だけでなく、ボランティアやNPO/NGOなどの市民活動団体が公共サービスの担い手として注目されています。これらの組織は、自発的に柔軟に問題を発見し、その解決に取り組んでいます。とりわけまちづくりやコミュニティ形成に対しては、行政と企業、市民が協力するパートナーシップ(協働)の役割分担について考えていく必要性が高まっています。ゼミの大きなテーマは、まちづくり、市民活動の展開、行政との協働、都市政策など、コミュニティで発生する問題を幅広く扱います。
ゼミでやること
西山ゼミでは基本文献の講読によってコミュニティに関する枠組みを確認した上で、障害者の自立支援や福祉政策、農村の地域再生、創造都市政策など、コミュニティをめぐる最先端の問題を取り上げ、それぞれが研究発表を行っています。どのような問題が発生し、それを解決するためにどのような活動が生み出されているのか、自ら考える力を高め、それをまとめるトレーニングを中心に行っています。
またそれだけでなくコミュニケーション能力を高めるために討論の時間をとり、相手に対してわかりやすく自分の意見を述べること、相手の意見をふまえて自分の意見を述べること、相手に対して論理的に反論することなどの練習を行いました。様々な社会問題、地域問題に対して、自らの考えを論理的にまとめ(logical thinking)、コミュニケーションを図るトレーニングを重視します。
またそれだけでなくコミュニケーション能力を高めるために討論の時間をとり、相手に対してわかりやすく自分の意見を述べること、相手の意見をふまえて自分の意見を述べること、相手に対して論理的に反論することなどの練習を行いました。様々な社会問題、地域問題に対して、自らの考えを論理的にまとめ(logical thinking)、コミュニケーションを図るトレーニングを重視します。
フィールドワークの実施

寿町でのフィールドワーク
2015年のゼミ合宿では、労働者の町、ドヤ街として有名な横浜寿町でフィールドワークを行い、そこで社会的排除や格差問題など、地域コミュニティが抱える問題について、とことん議論をしました。「現場から学ぶ」ということが、西山ゼミの基本姿勢です。
西山ゼミの三ヵ条
1、コミュニケーション能力を高めよう!
2、明るく、楽しいゼミにしよう!
3、ほう(報告)れん(連絡)そう(相談)を大切に!
2、明るく、楽しいゼミにしよう!
3、ほう(報告)れん(連絡)そう(相談)を大切に!
ゼミ生の声

2015年 横浜での合宿
「常識」を疑う。何でそれが「当たり前」として広まっているのか。社会学を始めたきっかけはとても身近で、日常の些細なところに転がっていました。このゼミに入ろうとしたのは、都市やコミュニティといった私たちの生活と切っても切れないトピックを に取り扱うゼミだったから。また、ゼミでの学びは教室の枠を超え、フィールドワークや ゲストスピーカーの方々と共に現代社会が抱える問題を多方面から分析していきます。学術的スキルのみならず、社会から必要とされているスキルも同時に鍛えられること。そして、何よりも人とのつながりを重宝しているゼミであることがこのゼミの特徴であり、資産だと確信しています。学生生活をより充実したものにする要素がたっぷりとつまった西山ゼミは、今の自分のキャリアに大きな影響を与えてくれました。
(2015年 社会学部社会学科4年 ゼミ長 山崎拓也)
(2015年 社会学部社会学科4年 ゼミ長 山崎拓也)
「地域社会を勉強したい!」そんな思いで西山ゼミを選びました。毎週、課題論文を読み込み議論する中で、「やっぱり社会学はおもしろい!」と心から思っています。論点を組み立てる「論理的思考力」。相手にわかりやすく伝える「コミュニケーション能力」や「プレゼンテーション能力」。社会に出ても必要な力が、主体的に取り組むほど身につきます。真剣な時は真剣に。楽しむ時はとことん楽しむ。同期や先輩後輩の繋がりを大切にする。そんなメンバーが、このゼミには集まっています。地域やコミュニティに関心がある人、社会学のおもしろさを学びたい人、西山ゼミをおすすめします!
(2015年 社会学部社会学科4年 副ゼミ長 山口鈴香)
(2015年 社会学部社会学科4年 副ゼミ長 山口鈴香)

ゼミの楽しい飲み会
西山ゼミの普段のゼミの雰囲気ですが、ゼミ生どうし(そして先生とも笑)仲が良く、とても楽しく活気あるものになっています。ゼミ合宿では3,4年で行くため学年の枠を超えてとても仲良くなれます。しかし、ただ楽しいだけではなくそれぞれが自分の意見を述べることで活発な議論ができていると思います。また、私は社会学や地域コミュニティについて真剣に向き合い考えるようになったのは西山ゼミに入ってからでした。深く学問を勉強するのは大変ですが必ずそこには普段の講義にはない面白さがあると思います。楽しいメンバー達と勉強も遊びも真剣なゼミ生活をおくってみませんか!!
(2015年 社会学部社会学科4年 副ゼミ長 荻原樹)
(2015年 社会学部社会学科4年 副ゼミ長 荻原樹)
都市空間とまちづくりの社会学

「大学生」という立場だとあまり実感しないのですが、私たちが現代社会のなかで生まれ育ち暮らすということは、実にさまざまな社会的ネットワークやサポートの網の内部に自らを置き続けるということです。家族・親族や近隣地域はもちろん、公私立の学校や各種公共施設、企業、交通体系、そして国家や世界社会に至るまでの複雑なシステムが私たち1人1人の平凡な日常生活を可能にし支えています。
このことは、皆さんがいわゆる「社会人」になり、結婚し家族を形成し家を買って仕事をし納税する…等々の場面で社会の側と多様な接点をもつにつれて、ある種のリアリティをもって感じられることでしょう。
このゼミでは、こうした「社会」のなかで生きるということの意味、「社会」はどのようなものとして私たちの前に立ち現れ、私たちはそれにどう対応しつつ暮らしているかの理解、要するに「社会」と「私」の接点の部分について深く学ぶことを目標とします。
そのとき、このゼミでの主たる舞台は、現代都市社会です。担当教員(野呂)が東京生まれ東京育ちというのが大きな理由なのですが、それを別にしても立教大学が池袋という副都心地区に立地しているメリットを生かさない手はないでしょう。現代都市の空間はとても魅力的であると同時に、常にダイナミックに動いており、それゆえ現代的な諸問題が最も発現する場でもあります。それらの問題や課題に日々対処している「社会」をできるだけ具体的な次元で見ていくところに、大きな知的刺激や面白さがあると思います。
そこで、ゼミでは、都市の空間や建物(家屋/オフィスビルなど)の中でさまざまに展開している地域社会の実情、人びとの社会生活をサポートしている自治体政策の現状と課題、町内会をはじめとする地域団体や各種ボランティア・NPOの活動などを、「一つの全体」として相互関連的に検討し、分析していきます。そのために、大学構内での講義だけでなく、積極的に外に出て街探索やフィールドワーク、インタビューを実施し、そうした実践の中で現代都市の有り様を考察していきたいと思います。これらの経験は、3年のゼミ論文報告書執筆という形で成果にしていき、4年次に1人1人が取り組んでいく卒業論文のための研究に生かすことができれば、と願っています。
このことは、皆さんがいわゆる「社会人」になり、結婚し家族を形成し家を買って仕事をし納税する…等々の場面で社会の側と多様な接点をもつにつれて、ある種のリアリティをもって感じられることでしょう。
このゼミでは、こうした「社会」のなかで生きるということの意味、「社会」はどのようなものとして私たちの前に立ち現れ、私たちはそれにどう対応しつつ暮らしているかの理解、要するに「社会」と「私」の接点の部分について深く学ぶことを目標とします。
そのとき、このゼミでの主たる舞台は、現代都市社会です。担当教員(野呂)が東京生まれ東京育ちというのが大きな理由なのですが、それを別にしても立教大学が池袋という副都心地区に立地しているメリットを生かさない手はないでしょう。現代都市の空間はとても魅力的であると同時に、常にダイナミックに動いており、それゆえ現代的な諸問題が最も発現する場でもあります。それらの問題や課題に日々対処している「社会」をできるだけ具体的な次元で見ていくところに、大きな知的刺激や面白さがあると思います。
そこで、ゼミでは、都市の空間や建物(家屋/オフィスビルなど)の中でさまざまに展開している地域社会の実情、人びとの社会生活をサポートしている自治体政策の現状と課題、町内会をはじめとする地域団体や各種ボランティア・NPOの活動などを、「一つの全体」として相互関連的に検討し、分析していきます。そのために、大学構内での講義だけでなく、積極的に外に出て街探索やフィールドワーク、インタビューを実施し、そうした実践の中で現代都市の有り様を考察していきたいと思います。これらの経験は、3年のゼミ論文報告書執筆という形で成果にしていき、4年次に1人1人が取り組んでいく卒業論文のための研究に生かすことができれば、と願っています。
ゼミ生の声
ゼミ代表 渡部 裕之
ゼミは必ずしも教室で行うものではない—ゼミとは本来、生徒が好き勝手意見を出し合い、好き勝手行動し、好き勝手好きな分野について研究する場であると思う。大学の講義は基本的につまらない教授の話を一方的に聞く受動型のものが多く、ゼミもそう思われがちである。しかし、貴重な大学生活を出席のためだけに出ているだけではもったいない。どうせゼミに入るなら自分が少しでも興味ある分野をとことん掘り下げて研究するべきである。そのためには、教室ではなく実社会のフィールドの中で活動するのもいいのではないかと思う。
当ゼミのスタイルは自由だ。教授がまだまだ新任ということもあり、一からゼミを創り上げている段階である。なので、型にはまったゼミに入るのが嫌であり、特にやりたいことがないけれど何かに思いっきり打ち込んでみたいと考えているのならば当ゼミはぴったりかもしれない。 基本的なテーマとして「都市と地域社会」について勉強をしているが、生徒によってはスポーツ、教育、文化など全く違った分野の研究をしている人がいるのも当ゼミならではの特徴なのではと思う。ゼミの内容に沿った分野でなくとも各自で好きなことを見つけ、それについてとことん研究することが出来るのも魅力的だと思う。
3年ゼミは指定された教室ではなく教授室で行っており、お菓子やお茶を飲みながらみんなで意見を出し合いながら話を勧めるスタイルである。また、主な活動として実際に教室を出て現場に触れるために、大学~目白高級住宅街~大久保コリアンタウン~新宿歌舞伎町まで街歩きを行った。また、夏合宿では合宿という名の下で熱海を観光し、温泉でゆったり過ごした。 また、ゼミ一年を通じて代官山のフィールドワークを行い、昔と今の代官山におけるイメージの違いや、そこに住む人々や働く労働者達の本音の部分を調査し、その中で形成されているネットワークについてまとめた。
ゼミのあり方なんて無限に存在すると思う。どれが一番かは分からない。しかし、本人自らがゼミを創り上げて、好きなことを学ぶことはとても素晴らしい経験になると思う。もし少しでも当ゼミに興味があれば気軽に飛び込んで欲しい。
ゼミは必ずしも教室で行うものではない—ゼミとは本来、生徒が好き勝手意見を出し合い、好き勝手行動し、好き勝手好きな分野について研究する場であると思う。大学の講義は基本的につまらない教授の話を一方的に聞く受動型のものが多く、ゼミもそう思われがちである。しかし、貴重な大学生活を出席のためだけに出ているだけではもったいない。どうせゼミに入るなら自分が少しでも興味ある分野をとことん掘り下げて研究するべきである。そのためには、教室ではなく実社会のフィールドの中で活動するのもいいのではないかと思う。
当ゼミのスタイルは自由だ。教授がまだまだ新任ということもあり、一からゼミを創り上げている段階である。なので、型にはまったゼミに入るのが嫌であり、特にやりたいことがないけれど何かに思いっきり打ち込んでみたいと考えているのならば当ゼミはぴったりかもしれない。 基本的なテーマとして「都市と地域社会」について勉強をしているが、生徒によってはスポーツ、教育、文化など全く違った分野の研究をしている人がいるのも当ゼミならではの特徴なのではと思う。ゼミの内容に沿った分野でなくとも各自で好きなことを見つけ、それについてとことん研究することが出来るのも魅力的だと思う。
3年ゼミは指定された教室ではなく教授室で行っており、お菓子やお茶を飲みながらみんなで意見を出し合いながら話を勧めるスタイルである。また、主な活動として実際に教室を出て現場に触れるために、大学~目白高級住宅街~大久保コリアンタウン~新宿歌舞伎町まで街歩きを行った。また、夏合宿では合宿という名の下で熱海を観光し、温泉でゆったり過ごした。 また、ゼミ一年を通じて代官山のフィールドワークを行い、昔と今の代官山におけるイメージの違いや、そこに住む人々や働く労働者達の本音の部分を調査し、その中で形成されているネットワークについてまとめた。
ゼミのあり方なんて無限に存在すると思う。どれが一番かは分からない。しかし、本人自らがゼミを創り上げて、好きなことを学ぶことはとても素晴らしい経験になると思う。もし少しでも当ゼミに興味があれば気軽に飛び込んで欲しい。
エスノメソドロジー——人々の方法論を実践から学ぶ
前田ゼミは、2018年度から始まった新しいゼミです。このゼミでは、私たちが社会生活を営む中で、自らや互いの経験や行為を理解するさいに用いている「人びとの方法論」について、私たちが参加している問題として理解し、分析し、問い直していきます。
人を対象とする学問である社会学が、自然科学と異なるのは、対象となっている人びとの側が、自分たちの行っていることや経験していることをどのように「理解」しているのか、考えなければならない、という点にあります。天体の移動を観察する天文学者なら、天体がどのような考えのもとで移動していくのかを、調べはしないでしょう。ところが、たとえばある病いを生きている人がどのような経験をしているのか知りたい、と考えるならば、その人が、身体の不調や痛みをどのように位置づけ、医療者から伝えられた情報をどのように理解し、さまざまなこととどのように折り合いをつけてきたかを、知ろうとするでしょう。そこには、その人自身が自らの経験を理解するために用いている「方法」があるはずです。
実際に私たちは、日常生活から病いの経験にいたるまで、何らかの方法を用いて自らや互いの経験や行為を理解し、社会生活を営んでいます。日常会話からはじまって、友人と議論をしたり、教室で学んだり、病院で診察を受けたり、テレビでCMを見たり、観光旅行にでかけたり、といったさまざまな実践にいたるまで、そこに参加している人たちは、実際に何らかの方法論を用いて、それぞれの実践を行っているのです。それならば、そこで用いられている「人びとの方法論」を研究してみよう、というのが基本的な出発点です。 こうした考え方を、「エスノメソドロジー(人びとの方法論)」と呼びます。
担当者自身は、こうした考え方のもとで、病いの当事者たちがどのような経験をしているのか、医療者たちがどのようなケアの実践をしているのか、といった調査研究をしています。そこで見いだされる「方法」は、それぞれに固有のものであるのと同時に、他の私たちの社会生活と地続きなものでもあります。自らの経験をどのように物語として語るのか、であるとか、他者の感情にどのように配慮するのか、であるとか、組織の中でどのように協働し分業するのか、といった問いは、さまざまな実践の中で見いだされる問いであり、それぞれの実践の参加者たち自身が問うている問いなのです。
基本的には、私たち自身が参加しうるさまざまな実践のすべてが、研究の対象になりえます。これらの実践のどこからでも出発できるので、ゼミ生のみなさんにも、自らの関心にあわせて問いを深めていくことが期待されます。また、それぞれの問いを深めていくために、このゼミでは、エスノメソドロジーを中心とした質的研究の方法の習得もサポ—トします。私たちが日常的に行ってしまっている社会生活の方法を問い直すこと、これがこのゼミで行っていく基本的な課題です。それぞれの問題関心と分析力を鍛えあげていきましょう。
人を対象とする学問である社会学が、自然科学と異なるのは、対象となっている人びとの側が、自分たちの行っていることや経験していることをどのように「理解」しているのか、考えなければならない、という点にあります。天体の移動を観察する天文学者なら、天体がどのような考えのもとで移動していくのかを、調べはしないでしょう。ところが、たとえばある病いを生きている人がどのような経験をしているのか知りたい、と考えるならば、その人が、身体の不調や痛みをどのように位置づけ、医療者から伝えられた情報をどのように理解し、さまざまなこととどのように折り合いをつけてきたかを、知ろうとするでしょう。そこには、その人自身が自らの経験を理解するために用いている「方法」があるはずです。
実際に私たちは、日常生活から病いの経験にいたるまで、何らかの方法を用いて自らや互いの経験や行為を理解し、社会生活を営んでいます。日常会話からはじまって、友人と議論をしたり、教室で学んだり、病院で診察を受けたり、テレビでCMを見たり、観光旅行にでかけたり、といったさまざまな実践にいたるまで、そこに参加している人たちは、実際に何らかの方法論を用いて、それぞれの実践を行っているのです。それならば、そこで用いられている「人びとの方法論」を研究してみよう、というのが基本的な出発点です。 こうした考え方を、「エスノメソドロジー(人びとの方法論)」と呼びます。
担当者自身は、こうした考え方のもとで、病いの当事者たちがどのような経験をしているのか、医療者たちがどのようなケアの実践をしているのか、といった調査研究をしています。そこで見いだされる「方法」は、それぞれに固有のものであるのと同時に、他の私たちの社会生活と地続きなものでもあります。自らの経験をどのように物語として語るのか、であるとか、他者の感情にどのように配慮するのか、であるとか、組織の中でどのように協働し分業するのか、といった問いは、さまざまな実践の中で見いだされる問いであり、それぞれの実践の参加者たち自身が問うている問いなのです。
基本的には、私たち自身が参加しうるさまざまな実践のすべてが、研究の対象になりえます。これらの実践のどこからでも出発できるので、ゼミ生のみなさんにも、自らの関心にあわせて問いを深めていくことが期待されます。また、それぞれの問いを深めていくために、このゼミでは、エスノメソドロジーを中心とした質的研究の方法の習得もサポ—トします。私たちが日常的に行ってしまっている社会生活の方法を問い直すこと、これがこのゼミで行っていく基本的な課題です。それぞれの問題関心と分析力を鍛えあげていきましょう。
行動科学の研究法-計量社会学と社会調査法

ゼミ発表会
平等と言われた日本社会も、ホームレスやフリーターが増える一方、ヒルズ族やセレブが話題となるなど、格差が目立つ社会となってきました。このゼミでは、社会階層研究や人々の価値観の変化、外国人問題、環境問題など、現代社会のさまざまな現象をとりあげ、社会現象が起こるメカニズムの解明に取り組みます。現実社会を分析できる人材を育成することがゼミの目的です。とくに、大規模な社会調査実施と、データ分析能力を重視します。できるだけ学際的に幅広く、かつ現実的、実証的に、研究を行うことが望まれます。これらを通して「データを分析して仕事を進める総合的能力」を身につけ、大学卒業後に生かすことができます。
批判的精神を養うことがゼミの最大の目的です。本や事典、教員の言うことなどが常に正しいとは限らず、現在の科学では分からないこともたくさんあります。ゼミでは、学術論文や学術書をもとに発表と討論の他、各種統計データ(マクロデータ)の収集と分析、実際の社会調査データ(ミクロデータ)の分析結果をもとにした討論、ゼミ論や卒論作成を行います。全学年合同での論文構想発表を中心としたゼミ合宿を年1度実施する他、ゲストスピーカー企画や、何度かのゼミコンパで、学年を超えた交流をし、楽しくかつ活発に学生達が活躍しています。
批判的精神を養うことがゼミの最大の目的です。本や事典、教員の言うことなどが常に正しいとは限らず、現在の科学では分からないこともたくさんあります。ゼミでは、学術論文や学術書をもとに発表と討論の他、各種統計データ(マクロデータ)の収集と分析、実際の社会調査データ(ミクロデータ)の分析結果をもとにした討論、ゼミ論や卒論作成を行います。全学年合同での論文構想発表を中心としたゼミ合宿を年1度実施する他、ゲストスピーカー企画や、何度かのゼミコンパで、学年を超えた交流をし、楽しくかつ活発に学生達が活躍しています。
特徴、卒論や就職

(左)ある日の3年ゼミ (右)ある日の4年ゼミ
データ分析の訓練や、実証性な現実社会の分析能力を重視することがゼミの特徴です。卒論は、世界十数カ国の調査データを統計的に分析したもの、自分で 800人以上の学生に統計的な調査をしたもの、大学外で社会人数十人に仕事と価値観などについて深くインタビューしたものなど、手法は様々です。目的に応じて手法を選ぶことこそが重要で、このゼミでは、特定の手法に限定しません。最新のデータ分析を行う人もいますし、卒論も十分な成果を挙げています。新聞社、大手コンサルティング会社、調査会社、通信会社、日銀や民間金融機関まで、就職が驚くほどいいのもこのゼミの特徴の一つです。ただし当然ながら、成果が出るのはやる気があって自主的に取り組む人です。先生の言うとおりに行動するのでなく、自分でテーマと研究計画を決めて進んでいく人が歓迎されます!
ゼミ生の声

ゼミ合宿 白子町にて
本格的な統計分析ソフトを使って、自分の好きなテーマについて分析できるゼミです。具体的な方法は授業内で先生が解説してくれるため、初心者でも安心です。ゼミ内のイベントとしては、夏のゼミ合宿や、定期的に開催される飲み会などがあり、みんな楽しく参加しています!(NK)
統計学は数学の延長線だと考えがちですが、実際の計算は分析ソフトを操作すれば簡単です。自分で調べた分析結果に基づいて、どんな因果関係があるのか考えてみるのは楽しいことです。結果を出した後、みんなと議論を行います。話し合うことが好きな人、分析について色々と考えるのが好きな人にお勧めです。(KT)
自分の興味のある社会事象を対象に研究を行うことが出来て、みんな研究内容が違うのでゼミの中で幅広い視野を得ることができます。主に統計データなどを使って分析を行うので説明力のある研究ができると思います。もちろん研究には真面目に取り組みますが、みんな仲良く全体的に雰囲気もとても楽しいです!(SA)
統計分析と聞くと難しいと感じてします人もいるかと思います。けれども、実際にデータに触れて、そこから結果を導き出していくことはとても楽しく、一番達成感があります。それが難しさの原因でもあるのですが・・・。また学年間の交流も盛んなゼミです。私はよく一つ上の先輩方の飲み会に参加させてもらい楽しく過ごしています。(NK)
各自で自分の好きなテーマについて、自由に分析しているゼミです!誰でも、社会統計学を一から学ぶことができます。年に一回のゼミ合宿では、2~4年生、院生が参加します。互いの研究経過を発表し、翌日には海で遊んだり、富士山を見ながらクルージングしたりと、学年を超えた交流があります!(SM)
このゼミの魅力は、まず統計的な分析力がつくことです。統計は難しそうに感じるかと思いますが、先生の説明は分かりやすいですし、何よりゼミ生同士で議論を交わしながら分析の練習を重ねることで着実に身につきます。そして様々な社会問題や社会現象を広い視野で捉えることができるようになります。また、調査テーマを各自自由に決めることができるので、議論の内容が豊かな充実した時間を過ごせます!(IY)
統計学は数学の延長線だと考えがちですが、実際の計算は分析ソフトを操作すれば簡単です。自分で調べた分析結果に基づいて、どんな因果関係があるのか考えてみるのは楽しいことです。結果を出した後、みんなと議論を行います。話し合うことが好きな人、分析について色々と考えるのが好きな人にお勧めです。(KT)
自分の興味のある社会事象を対象に研究を行うことが出来て、みんな研究内容が違うのでゼミの中で幅広い視野を得ることができます。主に統計データなどを使って分析を行うので説明力のある研究ができると思います。もちろん研究には真面目に取り組みますが、みんな仲良く全体的に雰囲気もとても楽しいです!(SA)
統計分析と聞くと難しいと感じてします人もいるかと思います。けれども、実際にデータに触れて、そこから結果を導き出していくことはとても楽しく、一番達成感があります。それが難しさの原因でもあるのですが・・・。また学年間の交流も盛んなゼミです。私はよく一つ上の先輩方の飲み会に参加させてもらい楽しく過ごしています。(NK)
各自で自分の好きなテーマについて、自由に分析しているゼミです!誰でも、社会統計学を一から学ぶことができます。年に一回のゼミ合宿では、2~4年生、院生が参加します。互いの研究経過を発表し、翌日には海で遊んだり、富士山を見ながらクルージングしたりと、学年を超えた交流があります!(SM)
このゼミの魅力は、まず統計的な分析力がつくことです。統計は難しそうに感じるかと思いますが、先生の説明は分かりやすいですし、何よりゼミ生同士で議論を交わしながら分析の練習を重ねることで着実に身につきます。そして様々な社会問題や社会現象を広い視野で捉えることができるようになります。また、調査テーマを各自自由に決めることができるので、議論の内容が豊かな充実した時間を過ごせます!(IY)

ゼミ合宿の一コマ
このゼミの特徴は統計学を用いて、日本社会を解明していくことです。この世界はありとあらゆる数字に支配されています。年収や偏差値、身長など例を挙げるときりがありません。私たちは主にこのような数値化されたものを統計ソフトを用いて分析し、日本社会の実態に迫ります。統計という客観的な目を通じて、自らが主体となって研究を進めていく。このことは、ただただ机に向かって論文を読むという研究を超えた面白さがあります。世界各国のデータを分析する人もいます。ゼミに入り、胸を張ってこれをやりきったという研究を共に作り出しませんか。(SK)
村瀬ゼミの特徴は、主に量的調査を用いて研究を行っていく所です。村瀬ゼミほど本格的な量的調査を学べるゼミは数少ないと思います。このゼミで学ぶと、例えば、人々の傾向などの漠然としたものを数値化し、その存在を証明できるようになります。また、研究テーマは基本的に自由なので、量的調査を用いて研究をしたい方はもちろん、自分のやりたいことが決まっていない方にもおすすめです!(OK)
村瀬ゼミの特徴は、主に量的調査を用いて研究を行っていく所です。村瀬ゼミほど本格的な量的調査を学べるゼミは数少ないと思います。このゼミで学ぶと、例えば、人々の傾向などの漠然としたものを数値化し、その存在を証明できるようになります。また、研究テーマは基本的に自由なので、量的調査を用いて研究をしたい方はもちろん、自分のやりたいことが決まっていない方にもおすすめです!(OK)

ゼミ合宿の一コマ
このゼミでは、分析する力をつけることができます。自分の興味あることについて立てた仮説を、データを使って分析しながら考えていくことができるので、論理的で説得力のある考え方が身に付きます。表やグラフを作ったり統計調査データを分析する能力は、社会に出てからも役に立つと思うので、オススメです!(AS)
このゼミは統計データを使って自分の好きな社会の事象を分析することができます。前期では社会階層に関する文献を読んで討論を行い、階層格差について見識を広めます。その上で夏以降自分が興味のあることを自由に選んで、全国規模の統計データを扱い分析していきます。探究心が強い人は是非村瀬ゼミに来てください。(FT)
このゼミは統計データを使って自分の好きな社会の事象を分析することができます。前期では社会階層に関する文献を読んで討論を行い、階層格差について見識を広めます。その上で夏以降自分が興味のあることを自由に選んで、全国規模の統計データを扱い分析していきます。探究心が強い人は是非村瀬ゼミに来てください。(FT)
